


Interview
美を追求する中でうまれる新たな価値と技術
株式会社細尾 代表取締役社長
細尾真孝さん
1978年生まれ。西陣織の老舗、細尾12代目。大学卒業後、音楽活動を経て、大手ジュエリーメーカーに入社。退社後フィレンツェに留学。2008年に細尾入社。西陣織の技術を活用した革新的なテキスタイルを海外に向けて展開。「ディオール」「シャネル」「エルメス」「カルティエ」の店舗やザ・リッツ・カールトンなどの5つ星ホテルに供給するなど、唯一無二のアートテキスタイルとして、世界のトップメゾンから高い支持を受けている。また、アーティストとのコラボレーションも積極的に行う。 2012年より京都の伝統工芸を担う同世代の後継者によるプロジェクト「GO ON」を結成。国内外で伝統工芸を広める活動を行う。 著書に『日本の美意識で世界初に挑む』
織物は京都に根付く産業であり、技術や機械、職人の技や美的感覚といった言語化しきれていない感性的な独自の価値はまさに『京都の文化』であると捉えることができる。文化価値を掘り下げること、特に織物と自然、環境との関係性を紐解いていくことは、人間の根源的な営みに触れる行為でもあり、永遠の探索でもある。京都から世界をリードする株式会社細尾代表取締役社長 細尾真孝さんは、おそらくその永遠のテーマに対して、真正面から挑み続ける挑戦者でもある。伝統は古きを良きとするのではなく、現代の新たな視点を取り入れながら、非連続の革新を成し遂げていく。それが、京都のスピリットの本質だ。これからの織物産業の新生はどのように生まれようとしているのか?どのような未来の可能性をどのように切り拓こうとしているのか? ロフトワーク クリエイティブディレクターの加藤あんがインタビューを実施した。
(1)土地の風土、社会のメディアである織物
加藤あん(以下、加藤):京都における伝統産業は自然との共生によってベースが形づくられていったのではないかと私自身は捉えています。また、現代においても産業や経済の未来を考える上で、自然との調和や環境保持を無視することはできないと思っています。産業と自然。その関係性を紐解いていく上で、まず、織物における染めと自然、環境との結びつきについて、細尾さんはどのように解釈されていますか。
細尾真孝(以下、細尾):仰る通り、染色と自然の関係性は非常に深いものです。織物や染色というのは、産地である土地の風土や歴史によって作られた人々の性格、そういうものをすべて知っている。ある意味メディアみたいなものだと考えています。私は4年の歳月をかけて、京都のみならず日本全国、北海道から沖縄までの約40カ所以上の産地を回って記録を取りました。そのような活動は、染織にまつわる様々なリサーチをしているHOSOO STUDIES(*1)の「The Story of Japanese Textiles(*2)」として取り組んでいます。
例えば徳島県の藍染。川はたまに氾濫するので染色されている方の家や工房に船がかけてあるんですね。氾濫は人的には災害であるという負の側面ももちろんありますが、氾濫することで土壌に栄養分が入り、それは藍の活力になる。ある種、氾濫とは自然との循環であると捉えることもできる。氾濫が起こることを想定した上で、川の側に家や工房を構えているんですよね。また、奄美大島における染色のシグネチャーは大島紬です。地元で採れたテーチ木から抽出した液で染めることを繰り返し、鉄分が豊富な泥深い水田に反物を入れると、鉄が化学反応を起こして、泥が貼り付きます。それを100回近く繰り返して泥染ができていきます。まさにその土地の風土、土地の水がないとできないことです。このように染色と自然は切り離すことのできない深い関係性にあります。
同時にまた、人と社会という関係性も切り離すことはできないですよね。越後上布は基本献上品として、つまり税金として納められたものです。とても細い糸を作り、手作業で丁寧に織っていきます。織り上げた布を「雪ざらし」といって、雪の積もってる季節に晒していくと、オゾンの力でどんどん漂白されていくんです。一方、沖縄では「海ざらし」といって、海の中に晒して、オゾンの力で漂白していきます。普段の日常着として着るものであれば、そこまでしないようなクオリティのレベルで、自然の力をうまく活用しながら献上品として徹底的に細かく作り上げるんです。
当時の社会的背景によって生まれた圧倒的な技術の力は、染色を調査することを通じて再解釈をしたり、価値の再定義をすることができると考えています。
加藤:京都の場合も、森や水といった自然環境が染色に与える影響はやはり大きいのでしょうか。
細尾:「HOSOO STUDIES」の活動の一環として、2020年に「古代染色研究所(*3)」をスタートさせました。そこでは、平安時代から実践されていた「自然染色」「植物染」の再現の研究をしています。
まず、染色にとって水が一番大事です。基本的には軟水の方が良い。京都の西陣は軟水です。水の他には植物の鮮度も大切です。「とれたてがいい、植物が持っているエネルギーが重要」というのは料理と一緒なんですよ。染色の際に媒染という工程があるのですが、色を布等に定着させる色止めのために化学反応を起こします。どのような媒染剤を使うかも重要で、昔からレシピがあるんです。
例えば冠位十二階で最も位の高い方しか着用できない「深紫」という色がありますが、日本紫という植物の根から色を取ります。何度も染め重ねて、色を作っていきます。その日本紫の焙煎剤には昔から椿の灰がいいと言われています。椿の枝葉を焼き、出来上がった灰を井戸水の軟水の水に浸してから濾すとアルカリ性の水ができますが、それを焙煎剤として使用し、色止めをすることによって、さらに色彩が際立ち鮮やかにすることが可能となります。
このようなものづくりは近代の経済合理性とは対極にある。圧倒的に手間がかかります。だからこそ後継者が少なくなってきている。一方で、徹底的な染色のあとには圧倒的な鮮やかな色と高い堅牢度が表れます。自然染色はくすんでいて、色落ちしやすいという印象があるかもしれませんが、すべてがそうではありません。しかるべき技術とそのステップをどこまで踏めるかということが「美」に求められています。平安時代の貴族同士は「美」で競い合っていたため、妥協せずに染色を施していました。圧倒的な「美」を表現しきるためには、植物や水など、自然における様々な要素が必要です。
少し話がずれるかもしれませんが、医者が薬を服用するときに使う、服用という言葉は、「服」に「用」という字で構成されていますよね。一説には、平安期の染色からきていると言われています。「服を着ること」が薬だったんですね。日本紫など自然染色の植物は漢方薬としても使われていました。日本紫は傷の炎症を抑える、治りを早める効能がありました。お殿様が寝込んでいる頭に鉢巻をつけていたりしますが、日本紫で染めたものでできていることが多い。つまり「美しいこと」と「健康」はイコールだった。
そのような意味では、自然を身に纏うことで人間は自然からエネルギーを得ることができた。染色という行為を媒介としながら、自然と人は共存していると考えることもできる。自然染色された糸で織られた布というものは、常に自然環境と人間の身体との間に在り続けるものではないかと私は解釈しています。
加藤:なるほど。そのように自然と染色の関係性を紐解いていくと、自然と人間の親密な関係性が構築されていた背景がよくわかりますね。自然を身に纏うことは、圧倒的な美へと人間を導くことにつながっている。染色という行為そのものが、自然と人間の共存的な関係性から生み出されたものであり、人間にとっては、美としてさらに独自の価値へと結晶化されたということでもあるのですね。
*1 HOSOO STUDIES:染織にまつわる研究開発部門。膨大な布の歴史の研究とともに、新しい布の開発を行っている。
*2 The Story of Japanese Textiles:日本国内33箇所の染織産地を訪ね歩き、古くから伝わる布の技巧や美しさを独自の視点で記録したドキュメンテーション・プロジェクト。
*3 古代染色研究所:1000年以上昔、日本において実践されていた「自然染色」「植物染」の研究を行う。

(2)美の追求によって生み出される技術と革新の種
加藤:経済合理性を優先させていくと、丁寧なものづくりと両立させるためのバランスは得てして取りづらくなるというのが一般的な傾向としてあると思います。西陣織を産業として発展させていくために、美の追求とビジネスとしての効率性のバランスをどのように取られていますか。HOSOOは美の追求にこだわり抜きながら、非連続の革新に挑み続けている印象がありますが、実際には、どのように経済合理性とのバランスを生み出しているのでしょうか。
細尾:私たちは基本的には顧客の方々からのオーダーを受けてからつくることを仕組みとしていますので、必要なものだけをつくっています。また手も使いますけど機械も使います。通常の西陣織は幅32センチですが、HOSOOは2010年、世界で初めて150センチ幅の日本式ジャガード織機(*4)を開発しました。150センチ幅の織機は世界中にあります。しかし、西陣織の技術はヒューマンスケールによって生まれました。まるで手で織っているかのように機械を操ることができないか、そんなことを考え開発すること自体が大変でした。ある意味、人と馬の関係のように、人が織機を操りながら体を拡張して織っていく、それが開発イメージの根底にありました。
経糸を上げ下げしながら、緯糸を入れて独自の模様を織り成していきます。昔は、経糸の上げ下げも人がやっていました。空引機が中国からやってきて、一人が4mぐらい登り、筬(おさ)を持ち上げることで経糸を上げる。経糸の筬との間に、下にいるもう一人が緯糸の筬を入れる。まるで、二人羽織みたいに息を合わせて織っていました。一日かけても数ミリしか織れません。反物一枚が織り上がるまでにだいたい1年間もかかるわけです。それを買う天皇・将軍・貴族がいたわけです。しかし、江戸から明治に入って、明治維新が起こり、社会の体制が大きく変わったことで。このように非常に高価な反物を買うことのできる公家や大名といった階級の人々が京都からいなくなってしまった。
そのような局面で、西陣はリオンからジャガード織機を持ち込みました。ジョゼフ・マリー・ジャカール氏が1801年にパンチカードと言って、穴の空いてるところだけ経糸があがるという、人が経糸を持ち上げた動きをプログラム化し、パンチカードを何百枚も用意することで一人で織ることができるようになりました。それまでは限られた人しか着ることができなかった究極の織物が、このイノベーションによって、民主化された。画期的な革新の瞬間でした。
余談ですけれど、パンチカードのインスピレーションを受け継ぎ、発明されたのがコンピュータになってるわけです。経糸が上がるか下がるか、バイナリーコード0/1になっていくと。つまりテクノロジーと手仕事、工芸ということとの関係値も実はかなり近いんです。むしろ工芸の美を追求していく中で、テクノロジーがまた生み出されていったということができるでしょう。
一人ひとりに合わせてオーダーメイドのものを多くの人に届けることができなかったから、工芸から工業へ変遷を遂げてきたわけですが、「オーダーメイドのマスプロダクション」ということも今はテクノロジーを駆使すれば、ひょっとしたらできるかもしれないですね。その方が人にとっては豊かですよね。
つまり規格化して大量に作るマスプロダクションはコストを下げていける一方で、規格にはまらない素材は排除され、規格にはまらない買い手は基本的にはターゲットされない。逆にオーダーメイドは、素材の持ち味を生かしながら一人ひとりに合わせて作っていくということはできるけども、大量に製造するには時間がかかります。だからこそ、私は一人ひとりに合わせかつ、ある程度必要な分を多くの方々に届けることができればベストじゃないかなと思っています。また時間がかかっても、そのようなオーダーメイドの良さはもちろんありますし、残ってくるような気がしますね。
加藤:様々なジャンルで西陣織を応用するのに、古今の技術横断が見直されているのがわかります。HOSOO STUDIESでは、スマートテキスタイルなどにもチャレンジされていますよね。
細尾:「Ambient Weaving(*5)」というプロジェクトですね。東京大学の筧康明研究室とZOZONEXTと2020年からやってるプロジェクトです。西陣のジャガードのもっている強みは、太い糸、細い糸、様々な糸を織りわけること、複雑なストラクチャーを作ることができることです。Ambient Weavingは、より先端的な特殊な素材を織り込む技術にトライすること、また電子回路のように織物の構造を作ることもできるのではないかということでスタートしたプロジェクトです。例えば、オーガニックLEDライトから糸をつくり、銅線と織り込んだ布を開発しました。
技術的な向上としては、これまでは、緯糸(よこいと)の領域のコントロールをコンピュータで制御していたところから、縦糸(たていと)緯糸を組み合わせて、256個にも及ぶドットそのものがコントロールできるようになりました。また、温度の変化を加えることによって、カラーを自由に出現させることができるようになりましたが、この技術革新の背景としては、「箔」という技術を生かし、特殊な顔料を塗布するなど、技術の応用をしています。いわゆる目に見えないものを可視化して織り込むことにトライする作品も新たに発表しています。
いわゆる平安期の自然染色から、現代のテクノロジーを駆使したような未来思考型のAmbient Weavingまで「環境と織物」という同様のテーマとして扱っています。織物には9000年の歴史があると言われていますが、常に織物は身体と環境との間に在り続けていることを前提としながら、さらに人と環境との在り方を深く考えていきたいというのもプロジェクトの大きなテーマでもあります。
また、「Quasicrystal(*6)」は3名のコンピュータプログラマーと一人の数学者と行っているプロジェクトで、9000年の歴史の中で、誰も生み出すことができなかった織物のストラクチャーを開発することを目的に進めています。
ロフトワーク 小川敦子(以下、小川):実際にお話を伺っていくと、織物とはとてもサイエンスの側面が強いのですね。サイエンスと人間の感性や身体性といった感覚が交錯している。また、非常に空間的な思考が、建築の世界にも近いと言いますか。織物とは、平面で捉えるのではなく、空間的に捉えていくと、またこれまでの見方が変わってきますね。
*4 150センチ幅の日本式ジャガード織機:一般的な西陣織の織機の幅は約34cm前後といわれる。これは着物の反物の幅に対応したもので、「一反」としての規格がこの幅だった。西陣織をインテリアや洋服などグローバルに展開するためにもより広幅の生地が求められた。
*5 Ambient Weaving:東京大学大学院情報学環筧康明研究室、ZOZO NEXTとともに「環境情報を表現する織物」「環境そのものが織り込まれた織物」をキーワードとして、織物に使用するマテリアル(素材)から織物の研究開発を行うプロジェクト。
*6 Quasicrystal:アーティスト/プログラマーの古舘健氏と共に、コンピュータ・プログラムによって、織物の根源的な構成要素である「織組織」を研究開発するプロジェクト。
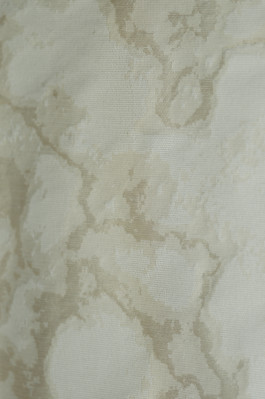

(3)究極の美、ラグジュアリーとは何か
加藤:近年、ラグジュアリーの定義は「華美さ」や「効率性」だけでは測れないものへと変化しつつあると感じます。たとえば、ブルネロ・クチネリの「人間的資本主義」に象徴されるように、地方の風景や人々の丁寧な暮らし、時間をかけたものづくりそのものが、豊かさの象徴として再評価されています。こうした文脈の中で、HOSOOにとって「ラグジュアリー」とは、どのような価値や在り方を指すのでしょうか?
細尾:ラグジュアリーの定義は時代ごとに変わってきますよね。変わる部分もあれば変わらない部分もあると考えています。私はラグジュアリーは美の定義にも近いなと感じています。西陣織はある美を上位概念におきながら始まっています。「究極の」という点でラグジュアリーのようなところもあると思います。茶の湯でさえ、もう利休以前と以降ではだいぶ定義が変わってきたと思いますし、それぞれの時代との関係性によって変化していきます。一方で何かタイムレスな、誰が見ても美しいっていうような、究極の「夕焼け」のような美ももちろんありますよね。そのようなバランスの中で、美の定義について考えています。
加藤:一貫した伝統的な思想を持ちながら新たな挑戦をされているんですね。細尾さんが思われる、伝統の継承とはどんなことでしょうか。
細尾:自分たちの活動は「伝統ど真ん中」だと思っています。というのは、現代において従来の着物のイメージから離れてく部分もあるかもしれませんが、まず自分たちのDNAは何なのかみたいなことから始まっています。僕らの場合、そのDNAは西陣織の「美と協業と革新」です。
「美」というのは、「究極」を追求して1000年間続けていますよね。そもそも暖を取るだけだったら毛皮を巻いていればよいはずが、わざわざ木の繊維を手で分解して糸にして織るという、どうしてそこまで手間暇をかけて、人は美を追求したのでしょう。私自身の中では、非常に興味深い視点です。
また、「協業」に関しては、西陣織はおよそ20工程があり、それぞれ1工程につき1名のマスタークラフツマンが担当し、約20人の職人の力で完成します。近年のように効率化のための分業ではなくて、究極の美を体現するための分業です。この工程はまだ西陣でも残っています。
最後に「革新」についてですが、江戸時代から明治に移り変わるタイミングでも、技術変革も含めて、大きなイノベーションが起きています。様々な時代の変化という大きな波の中で、イノベーションを起こすことによって時代がつながれてきています。つまり、伝統であることは、革新を続けてきてるからこそであり、挑戦して変わり続けてきたからこその伝統なのです。HOSOO STUDIESも美を上位概念におきながら研究しているので、シンプルに捉えています。つまり、「伝統を守る」ことは「未来に繋ぐ」ということだと思います。そのためには常に挑戦して革新し続けることが必要です。
細尾では、「着物(和服)に興味ないの?」と言われてしまうこともあるのですが、伝統的な着物(和服)は今でも全体の事業の内、約50%を占めています。また、海外で展開しているインテリアや、プロダクト、ファッションが「着物」ではないという考え方はしていません。両者ともに「織物」ということ、そもそも着物の定義というのは「着る物」ですよね。西洋からしたら洋服も着物ですし、またインテリアも着せていくと部屋の着物でもあるわけです。
やってることは時代に合わせていますが、変わらない部分に美があります。紋様ってなくてもいいものをなぜ人はいれるのか。そこが非常に興味がありますし、いろいろなことをやっているように見えるかもしれませんが、すべて一貫しているように感じます。
加藤:なるほど。世界的に活躍されてるアーティストやクリエイターとのコラボレーションをする中で、細尾さんとしては譲れないところ、また“らしさ”はどういうところにあると思いますか。
細尾:ずばり「美しさの追求」ですね。美って何なのかという終わりのない問いの続きではあるのですが、やっぱり見て美しいものって確かにあるんですね。 僕らはものづくりのモットーで、「More than Textile」を掲げています。常に織物の常識を超え続けていくことです。
ミラノデザインウィークにあわせて、年に一度新作を発表します。基本的には焼き回しみたいなことは行わなくて、その年に出したアイデアとかアプローチと似たようなものはやらないので、毎年、常にハードルが上がっていきます。 本当にいいものができなければ、最終決断「出さない」という判断もします。2~3年出せなかった時期もありました。
ハードルが上がっているなかで新作を発表できるのは、HOSOO STUDIESという研究開発があるからです。数ヶ月ちょっとリサーチして制作をするだけでは、突破できません。何年もリサーチすることで、いつかの新作につながるかもしれないと考えています。普通だったらやらなくてもいいと思われるようなことをわざわざやってる理由は、そういうことです。そうしないと、どこかで行き詰まってしまいますから。


(4)異なる専門性を持った人と思考する新しい物づくり
加藤:HOSOO STUDIESが制作プロジェクトを支えていることはわかりました。HOSOOにとって顧客との関係性、ものづくりのスタンスをお聞きしたいです。
細尾:日々のお客様とのプロジェクトに関しても、自分たちは「サプライヤー」ではなくて「コラボレーター」にどうなれるかという挑戦もずっと意識しています。サプライヤーは相手が求めているものを供給すればなれるわけですが、コラボレーターは相手が思っているもの以上、思ってもいなかったところ、それ以上のところまで、セッションをすることによってなれると考え、この人たちとセッションすると面白そうだなと思っていただけるようなスタンスでものづくりをしています。
小川:細尾さんが考える美のアップデートに対して、相手が面白いと感じることができれば、コラボレーターになる流れになってくる。そうなると、ライブ感覚のような美のセッションができる。それが結果的に営みとして循環しているのだろうと感じました。このような「美と協業と革新」が循環していくような手法として体系化されたのは、いつぐらいのことですか?
細尾:ちょうど私自身が代表になったのは、2020年ですが、まさにコロナ禍のタイミングでした。一気に世の中の雰囲気は変わりましたよね。まさに織物、着物において不要不急に捉えられる面もあったと思います。しかし、本当にそうなのかと。昔も飢饉などはあった中で、美というものは残ってきていることから、西陣のことも含めて、自分たちのDNAがどこにあるのか考えたときから、これまでやってきたことを再定義するようになりました。
その中でも、「協業」が重要だと感じています。協業から美が生まれ、協業から革新が生まれます。コンピュータプログラマーや数学者、海外アーティストとの協業により、今の時代しか実現できない織物や作品が生まれると考えています。もちろん、僕らを知らない人に知ってもらうためにはまだまだ道半ばではあります。西陣が海外で本格的にスタートしたのは2010年ですから、まだまだ始まったばかりだと感じています。
加藤:「The Mind Landscape(*7)」はイタリアの著名建築家でありデザイナーであるミケーレ・デ・ルッキが率いるスタジオAMDL CIRCLEとHOSOOの協業により生まれたコレクションですが、ミケーレ・デ・ルッキの「自然の驚異的な力と人間のはかない本質の間に立っている」建築家としての視点がテキスタイルとも共鳴した素晴らしいインスタレーションでもあると感じました。ミケーレ・デ・ルッキとはどのようなきっかけで協業されたのですか。
細尾:去年、僕らはミラノのブレラという地域でショールームをオープンしました。ブレラは17世紀に建てられた歴史的な建物の中にあります。ミケーレ・デ・ルッキ氏は前々から存じ上げていましたが、建築のみならず思想や哲学が素晴らしいと思っていました。ミラノのショールームがミケーレ・デ・ルッキのスタジオの近くだったんです。そういうご縁もあり、ショールームにきていただいたのがきっかけです。ミケーレ・デ・ルッキ氏は早い段階から、自然と人との共生をテーマにしていましたし、職人の工芸性やものづくりを重要視しています。だからこそ、セッションしたら、一体どんな織物ができるんだろうと思っていました。
The Mind Landscapeというシリーズは、基本的には「ミクロ、マクロ、人」という3つの視点で構成されています。1つ目は織物のパターンは「マクロな視点」で顕微鏡で木を覗いたときの細胞、2つ目は「ミクロの視点」で地球の外から地球や森をみたときの衛星写真です。このようなミクロとマクロの2つの視点を一つの織物の内に調和させました。さらに3つ目は、「職人の視点」によって初めて織物ができるという人の視点をコンセプトにしています。僕らも、並行して、人と自然の関わりなどについてリサーチをしていきました。
加藤:先ほどの話で織物とアーキテクチャという視点がありましたが、建築とテキスタイルという異なる領域を合わせたのはどのような意図があるのでしょう。
細尾:建築と織物は非常に似ています。織物もアーキテクチャです。また、織物には構造計算が必要です。経糸と緯糸の絶妙な均衡関係を捉えることでつくられます。柔らかいもの、身体に近いものではありますが、環境と人との間に在るものは、実は建築と非常に似ていると捉えています。
小川:実は空間的な構造体である織物を建築とコラボレーションさせることによって、改めて、その本質を浮かび上がらせたというのが、The Mind Landscapeというコレクションでもあるのだと、改めて、理解が深まりました。コレクションの布が1枚そこに佇むだけで、森の奥深くにつながっているかのような、不思議な錯覚と言いますか、非常に空間的な世界観を観せていただいたような感覚になりながら、コレクションを拝見していました。
細尾:織物は3Dです。遊牧民のゲルなど織物の建築物もあります。2016年に遊牧民族と共同生活をしたことがあります。ゲルは枠を木、外側は帆布で、内側は断熱材としてのフェルト、織物の装飾で構築されている 織物の建築です。そのような意味では、コンクリートなのか、木なのか、木綿なのかという素材の違いだけですね。
加藤:では、最後に、文化的な側面から社会と接続した新しいアプローチをしていく文化起業家やデザイナー、新たな領域で未来に挑戦する若き起業家の方々に対して、革新していくためのメッセージをお願いします。
細尾:文化や伝統を繋いでいくことは絶対一人の世代にはできないです。いかに挑戦してまたこのバトンを繋ぐか、また次の世代の人たちがバトンを受け継いで、挑戦して、また、次の世代にバトンを繋ぐ。
伝統を守るためにはもう、攻め続けて革新し続けないと守れません。もちろん、その中で変わらない部分があります。革新した中で残ったものは変えてはならない部分であって、常識や固定観念で決めてしまうと、そこにのみ込まれてしまう。 だからこそ、挑戦し続けています。
加藤:バトンを渡し続けていくことで、美という伝統が継承され、革新の連続が生まれてくるということですね。本日は大変貴重なお話をありがとうございました。
*7 The Mind Landscape:ミラノデザインウィークにて発表されたHOSOOの新作テキスタイル・コレクション「The Mind Landscape」を紹介した展覧会。イタリアの著名な建築家でありデザイナーであるミケーレ・デ・ルッキ率いるスタジオAMDL CIRCLEとHOSOOの協業のもと制作された。
Interview



美を追求する中でうまれる新たな価値と技術
株式会社細尾 代表取締役社長
細尾真孝さん
1978年生まれ。西陣織の老舗、細尾12代目。大学卒業後、音楽活動を経て、大手ジュエリーメーカーに入社。退社後フィレンツェに留学。2008年に細尾入社。西陣織の技術を活用した革新的なテキスタイルを海外に向けて展開。「ディオール」「シャネル」「エルメス」「カルティエ」の店舗やザ・リッツ・カールトンなどの5つ星ホテルに供給するなど、唯一無二のアートテキスタイルとして、世界のトップメゾンから高い支持を受けている。また、アーティストとのコラボレーションも積極的に行う。 2012年より京都の伝統工芸を担う同世代の後継者によるプロジェクト「GO ON」を結成。国内外で伝統工芸を広める活動を行う。 著書に『日本の美意識で世界初に挑む』
織物は京都に根付く産業であり、技術や機械、職人の技や美的感覚といった言語化しきれていない感性的な独自の価値はまさに『京都の文化』であると捉えることができる。文化価値を掘り下げること、特に織物と自然、環境との関係性を紐解いていくことは、人間の根源的な営みに触れる行為でもあり、永遠の探索でもある。京都から世界をリードする株式会社細尾代表取締役社長 細尾真孝さんは、おそらくその永遠のテーマに対して、真正面から挑み続ける挑戦者でもある。伝統は古きを良きとするのではなく、現代の新たな視点を取り入れながら、非連続の革新を成し遂げていく。それが、京都のスピリットの本質だ。これからの織物産業の新生はどのように生まれようとしているのか?どのような未来の可能性をどのように切り拓こうとしているのか? ロフトワーク クリエイティブディレクターの加藤あんがインタビューを実施した。
(1)土地の風土、社会のメディアである織物
加藤あん(以下、加藤):京都における伝統産業は自然との共生によってベースが形づくられていったのではないかと私自身は捉えています。また、現代においても産業や経済の未来を考える上で、自然との調和や環境保持を無視することはできないと思っています。産業と自然。その関係性を紐解いていく上で、まず、織物における染めと自然、環境との結びつきについて、細尾さんはどのように解釈されていますか。
細尾真孝(以下、細尾):仰る通り、染色と自然の関係性は非常に深いものです。織物や染色というのは、産地である土地の風土や歴史によって作られた人々の性格、そういうものをすべて知っている。ある意味メディアみたいなものだと考えています。私は4年の歳月をかけて、京都のみならず日本全国、北海道から沖縄までの約40カ所以上の産地を回って記録を取りました。そのような活動は、染織にまつわる様々なリサーチをしているHOSOO STUDIES(*1)の「The Story of Japanese Textiles(*2)」として取り組んでいます。
例えば徳島県の藍染。川はたまに氾濫するので染色されている方の家や工房に船がかけてあるんですね。氾濫は人的には災害であるという負の側面ももちろんありますが、氾濫することで土壌に栄養分が入り、それは藍の活力になる。ある種、氾濫とは自然との循環であると捉えることもできる。氾濫が起こることを想定した上で、川の側に家や工房を構えているんですよね。また、奄美大島における染色のシグネチャーは大島紬です。地元で採れたテーチ木から抽出した液で染めることを繰り返し、鉄分が豊富な泥深い水田に反物を入れると、鉄が化学反応を起こして、泥が貼り付きます。それを100回近く繰り返して泥染ができていきます。まさにその土地の風土、土地の水がないとできないことです。このように染色と自然は切り離すことのできない深い関係性にあります。
同時にまた、人と社会という関係性も切り離すことはできないですよね。越後上布は基本献上品として、つまり税金として納められたものです。とても細い糸を作り、手作業で丁寧に織っていきます。織り上げた布を「雪ざらし」といって、雪の積もってる季節に晒していくと、オゾンの力でどんどん漂白されていくんです。一方、沖縄では「海ざらし」といって、海の中に晒して、オゾンの力で漂白していきます。普段の日常着として着るものであれば、そこまでしないようなクオリティのレベルで、自然の力をうまく活用しながら献上品として徹底的に細かく作り上げるんです。
当時の社会的背景によって生まれた圧倒的な技術の力は、染色を調査することを通じて再解釈をしたり、価値の再定義をすることができると考えています。
加藤:京都の場合も、森や水といった自然環境が染色に与える影響はやはり大きいのでしょうか。
細尾:「HOSOO STUDIES」の活動の一環として、2020年に「古代染色研究所(*3)」をスタートさせました。そこでは、平安時代から実践されていた「自然染色」「植物染」の再現の研究をしています。
まず、染色にとって水が一番大事です。基本的には軟水の方が良い。京都の西陣は軟水です。水の他には植物の鮮度も大切です。「とれたてがいい、植物が持っているエネルギーが重要」というのは料理と一緒なんですよ。染色の際に媒染という工程があるのですが、色を布等に定着させる色止めのために化学反応を起こします。どのような媒染剤を使うかも重要で、昔からレシピがあるんです。
例えば冠位十二階で最も位の高い方しか着用できない「深紫」という色がありますが、日本紫という植物の根から色を取ります。何度も染め重ねて、色を作っていきます。その日本紫の焙煎剤には昔から椿の灰がいいと言われています。椿の枝葉を焼き、出来上がった灰を井戸水の軟水の水に浸してから濾すとアルカリ性の水ができますが、それを焙煎剤として使用し、色止めをすることによって、さらに色彩が際立ち鮮やかにすることが可能となります。
このようなものづくりは近代の経済合理性とは対極にある。圧倒的に手間がかかります。だからこそ後継者が少なくなってきている。一方で、徹底的な染色のあとには圧倒的な鮮やかな色と高い堅牢度が表れます。自然染色はくすんでいて、色落ちしやすいという印象があるかもしれませんが、すべてがそうではありません。しかるべき技術とそのステップをどこまで踏めるかということが「美」に求められています。平安時代の貴族同士は「美」で競い合っていたため、妥協せずに染色を施していました。圧倒的な「美」を表現しきるためには、植物や水など、自然における様々な要素が必要です。
少し話がずれるかもしれませんが、医者が薬を服用するときに使う、服用という言葉は、「服」に「用」という字で構成されていますよね。一説には、平安期の染色からきていると言われています。「服を着ること」が薬だったんですね。日本紫など自然染色の植物は漢方薬としても使われていました。日本紫は傷の炎症を抑える、治りを早める効能がありました。お殿様が寝込んでいる頭に鉢巻をつけていたりしますが、日本紫で染めたものでできていることが多い。つまり「美しいこと」と「健康」はイコールだった。
そのような意味では、自然を身に纏うことで人間は自然からエネルギーを得ることができた。染色という行為を媒介としながら、自然と人は共存していると考えることもできる。自然染色された糸で織られた布というものは、常に自然環境と人間の身体との間に在り続けるものではないかと私は解釈しています。
加藤:なるほど。そのように自然と染色の関係性を紐解いていくと、自然と人間の親密な関係性が構築されていた背景がよくわかりますね。自然を身に纏うことは、圧倒的な美へと人間を導くことにつながっている。染色という行為そのものが、自然と人間の共存的な関係性から生み出されたものであり、人間にとっては、美としてさらに独自の価値へと結晶化されたということでもあるのですね。
*1 HOSOO STUDIES:染織にまつわる研究開発部門。膨大な布の歴史の研究とともに、新しい布の開発を行っている。
*2 The Story of Japanese Textiles:日本国内33箇所の染織産地を訪ね歩き、古くから伝わる布の技巧や美しさを独自の視点で記録したドキュメンテーション・プロジェクト。
*3 古代染色研究所:1000年以上昔、日本において実践されていた「自然染色」「植物染」の研究を行う。

(2)美の追求によって生み出される技術と革新の種
加藤:経済合理性を優先させていくと、丁寧なものづくりと両立させるためのバランスは得てして取りづらくなるというのが一般的な傾向としてあると思います。西陣織を産業として発展させていくために、美の追求とビジネスとしての効率性のバランスをどのように取られていますか。HOSOOは美の追求にこだわり抜きながら、非連続の革新に挑み続けている印象がありますが、実際には、どのように経済合理性とのバランスを生み出しているのでしょうか。
細尾:私たちは基本的には顧客の方々からのオーダーを受けてからつくることを仕組みとしていますので、必要なものだけをつくっています。また手も使いますけど機械も使います。通常の西陣織は幅32センチですが、HOSOOは2010年、世界で初めて150センチ幅の日本式ジャガード織機(*4)を開発しました。150センチ幅の織機は世界中にあります。しかし、西陣織の技術はヒューマンスケールによって生まれました。まるで手で織っているかのように機械を操ることができないか、そんなことを考え開発すること自体が大変でした。ある意味、人と馬の関係のように、人が織機を操りながら体を拡張して織っていく、それが開発イメージの根底にありました。
経糸を上げ下げしながら、緯糸を入れて独自の模様を織り成していきます。昔は、経糸の上げ下げも人がやっていました。空引機が中国からやってきて、一人が4mぐらい登り、筬(おさ)を持ち上げることで経糸を上げる。経糸の筬との間に、下にいるもう一人が緯糸の筬を入れる。まるで、二人羽織みたいに息を合わせて織っていました。一日かけても数ミリしか織れません。反物一枚が織り上がるまでにだいたい1年間もかかるわけです。それを買う天皇・将軍・貴族がいたわけです。しかし、江戸から明治に入って、明治維新が起こり、社会の体制が大きく変わったことで。このように非常に高価な反物を買うことのできる公家や大名といった階級の人々が京都からいなくなってしまった。
そのような局面で、西陣はリオンからジャガード織機を持ち込みました。ジョゼフ・マリー・ジャカール氏が1801年にパンチカードと言って、穴の空いてるところだけ経糸があがるという、人が経糸を持ち上げた動きをプログラム化し、パンチカードを何百枚も用意することで一人で織ることができるようになりました。それまでは限られた人しか着ることができなかった究極の織物が、このイノベーションによって、民主化された。画期的な革新の瞬間でした。
余談ですけれど、パンチカードのインスピレーションを受け継ぎ、発明されたのがコンピュータになってるわけです。経糸が上がるか下がるか、バイナリーコード0/1になっていくと。つまりテクノロジーと手仕事、工芸ということとの関係値も実はかなり近いんです。むしろ工芸の美を追求していく中で、テクノロジーがまた生み出されていったということができるでしょう。
一人ひとりに合わせてオーダーメイドのものを多くの人に届けることができなかったから、工芸から工業へ変遷を遂げてきたわけですが、「オーダーメイドのマスプロダクション」ということも今はテクノロジーを駆使すれば、ひょっとしたらできるかもしれないですね。その方が人にとっては豊かですよね。
つまり規格化して大量に作るマスプロダクションはコストを下げていける一方で、規格にはまらない素材は排除され、規格にはまらない買い手は基本的にはターゲットされない。逆にオーダーメイドは、素材の持ち味を生かしながら一人ひとりに合わせて作っていくということはできるけども、大量に製造するには時間がかかります。だからこそ、私は一人ひとりに合わせかつ、ある程度必要な分を多くの方々に届けることができればベストじゃないかなと思っています。また時間がかかっても、そのようなオーダーメイドの良さはもちろんありますし、残ってくるような気がしますね。
加藤:様々なジャンルで西陣織を応用するのに、古今の技術横断が見直されているのがわかります。HOSOO STUDIESでは、スマートテキスタイルなどにもチャレンジされていますよね。
細尾:「Ambient Weaving(*5)」というプロジェクトですね。東京大学の筧康明研究室とZOZONEXTと2020年からやってるプロジェクトです。西陣のジャガードのもっている強みは、太い糸、細い糸、様々な糸を織りわけること、複雑なストラクチャーを作ることができることです。Ambient Weavingは、より先端的な特殊な素材を織り込む技術にトライすること、また電子回路のように織物の構造を作ることもできるのではないかということでスタートしたプロジェクトです。例えば、オーガニックLEDライトから糸をつくり、銅線と織り込んだ布を開発しました。
技術的な向上としては、これまでは、緯糸(よこいと)の領域のコントロールをコンピュータで制御していたところから、縦糸(たていと)緯糸を組み合わせて、256個にも及ぶドットそのものがコントロールできるようになりました。また、温度の変化を加えることによって、カラーを自由に出現させることができるようになりましたが、この技術革新の背景としては、「箔」という技術を生かし、特殊な顔料を塗布するなど、技術の応用をしています。いわゆる目に見えないものを可視化して織り込むことにトライする作品も新たに発表しています。
いわゆる平安期の自然染色から、現代のテクノロジーを駆使したような未来思考型のAmbient Weavingまで「環境と織物」という同様のテーマとして扱っています。織物には9000年の歴史があると言われていますが、常に織物は身体と環境との間に在り続けていることを前提としながら、さらに人と環境との在り方を深く考えていきたいというのもプロジェクトの大きなテーマでもあります。
また、「Quasicrystal(*6)」は3名のコンピュータプログラマーと一人の数学者と行っているプロジェクトで、9000年の歴史の中で、誰も生み出すことができなかった織物のストラクチャーを開発することを目的に進めています。
ロフトワーク 小川敦子(以下、小川):実際にお話を伺っていくと、織物とはとてもサイエンスの側面が強いのですね。サイエンスと人間の感性や身体性といった感覚が交錯している。また、非常に空間的な思考が、建築の世界にも近いと言いますか。織物とは、平面で捉えるのではなく、空間的に捉えていくと、またこれまでの見方が変わってきますね。
*4 150センチ幅の日本式ジャガード織機:一般的な西陣織の織機の幅は約34cm前後といわれる。これは着物の反物の幅に対応したもので、「一反」としての規格がこの幅だった。西陣織をインテリアや洋服などグローバルに展開するためにもより広幅の生地が求められた。
*5 Ambient Weaving:東京大学大学院情報学環筧康明研究室、ZOZO NEXTとともに「環境情報を表現する織物」「環境そのものが織り込まれた織物」をキーワードとして、織物に使用するマテリアル(素材)から織物の研究開発を行うプロジェクト。
*6 Quasicrystal:アーティスト/プログラマーの古舘健氏と共に、コンピュータ・プログラムによって、織物の根源的な構成要素である「織組織」を研究開発するプロジェクト。
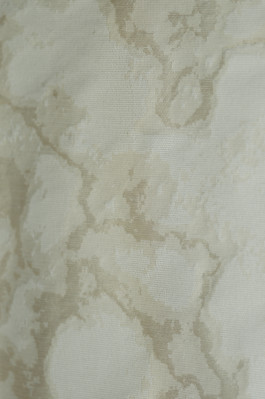

(3)究極の美、ラグジュアリーとは何か
加藤:近年、ラグジュアリーの定義は「華美さ」や「効率性」だけでは測れないものへと変化しつつあると感じます。たとえば、ブルネロ・クチネリの「人間的資本主義」に象徴されるように、地方の風景や人々の丁寧な暮らし、時間をかけたものづくりそのものが、豊かさの象徴として再評価されています。こうした文脈の中で、HOSOOにとって「ラグジュアリー」とは、どのような価値や在り方を指すのでしょうか?
細尾:ラグジュアリーの定義は時代ごとに変わってきますよね。変わる部分もあれば変わらない部分もあると考えています。私はラグジュアリーは美の定義にも近いなと感じています。西陣織はある美を上位概念におきながら始まっています。「究極の」という点でラグジュアリーのようなところもあると思います。茶の湯でさえ、もう利休以前と以降ではだいぶ定義が変わってきたと思いますし、それぞれの時代との関係性によって変化していきます。一方で何かタイムレスな、誰が見ても美しいっていうような、究極の「夕焼け」のような美ももちろんありますよね。そのようなバランスの中で、美の定義について考えています。
加藤:一貫した伝統的な思想を持ちながら新たな挑戦をされているんですね。細尾さんが思われる、伝統の継承とはどんなことでしょうか。
細尾:自分たちの活動は「伝統ど真ん中」だと思っています。というのは、現代において従来の着物のイメージから離れてく部分もあるかもしれませんが、まず自分たちのDNAは何なのかみたいなことから始まっています。僕らの場合、そのDNAは西陣織の「美と協業と革新」です。
「美」というのは、「究極」を追求して1000年間続けていますよね。そもそも暖を取るだけだったら毛皮を巻いていればよいはずが、わざわざ木の繊維を手で分解して糸にして織るという、どうしてそこまで手間暇をかけて、人は美を追求したのでしょう。私自身の中では、非常に興味深い視点です。
また、「協業」に関しては、西陣織はおよそ20工程があり、それぞれ1工程につき1名のマスタークラフツマンが担当し、約20人の職人の力で完成します。近年のように効率化のための分業ではなくて、究極の美を体現するための分業です。この工程はまだ西陣でも残っています。
最後に「革新」についてですが、江戸時代から明治に移り変わるタイミングでも、技術変革も含めて、大きなイノベーションが起きています。様々な時代の変化という大きな波の中で、イノベーションを起こすことによって時代がつながれてきています。つまり、伝統であることは、革新を続けてきてるからこそであり、挑戦して変わり続けてきたからこその伝統なのです。HOSOO STUDIESも美を上位概念におきながら研究しているので、シンプルに捉えています。つまり、「伝統を守る」ことは「未来に繋ぐ」ということだと思います。そのためには常に挑戦して革新し続けることが必要です。
細尾では、「着物(和服)に興味ないの?」と言われてしまうこともあるのですが、伝統的な着物(和服)は今でも全体の事業の内、約50%を占めています。また、海外で展開しているインテリアや、プロダクト、ファッションが「着物」ではないという考え方はしていません。両者ともに「織物」ということ、そもそも着物の定義というのは「着る物」ですよね。西洋からしたら洋服も着物ですし、またインテリアも着せていくと部屋の着物でもあるわけです。
やってることは時代に合わせていますが、変わらない部分に美があります。紋様ってなくてもいいものをなぜ人はいれるのか。そこが非常に興味がありますし、いろいろなことをやっているように見えるかもしれませんが、すべて一貫しているように感じます。
加藤:なるほど。世界的に活躍されてるアーティストやクリエイターとのコラボレーションをする中で、細尾さんとしては譲れないところ、また“らしさ”はどういうところにあると思いますか。
細尾:ずばり「美しさの追求」ですね。美って何なのかという終わりのない問いの続きではあるのですが、やっぱり見て美しいものって確かにあるんですね。 僕らはものづくりのモットーで、「More than Textile」を掲げています。常に織物の常識を超え続けていくことです。
ミラノデザインウィークにあわせて、年に一度新作を発表します。基本的には焼き回しみたいなことは行わなくて、その年に出したアイデアとかアプローチと似たようなものはやらないので、毎年、常にハードルが上がっていきます。 本当にいいものができなければ、最終決断「出さない」という判断もします。2~3年出せなかった時期もありました。
ハードルが上がっているなかで新作を発表できるのは、HOSOO STUDIESという研究開発があるからです。数ヶ月ちょっとリサーチして制作をするだけでは、突破できません。何年もリサーチすることで、いつかの新作につながるかもしれないと考えています。普通だったらやらなくてもいいと思われるようなことをわざわざやってる理由は、そういうことです。そうしないと、どこかで行き詰まってしまいますから。


(4)異なる専門性を持った人と思考する新しい物づくり
加藤:HOSOO STUDIESが制作プロジェクトを支えていることはわかりました。HOSOOにとって顧客との関係性、ものづくりのスタンスをお聞きしたいです。
細尾:日々のお客様とのプロジェクトに関しても、自分たちは「サプライヤー」ではなくて「コラボレーター」にどうなれるかという挑戦もずっと意識しています。サプライヤーは相手が求めているものを供給すればなれるわけですが、コラボレーターは相手が思っているもの以上、思ってもいなかったところ、それ以上のところまで、セッションをすることによってなれると考え、この人たちとセッションすると面白そうだなと思っていただけるようなスタンスでものづくりをしています。
小川:細尾さんが考える美のアップデートに対して、相手が面白いと感じることができれば、コラボレーターになる流れになってくる。そうなると、ライブ感覚のような美のセッションができる。それが結果的に営みとして循環しているのだろうと感じました。このような「美と協業と革新」が循環していくような手法として体系化されたのは、いつぐらいのことですか?
細尾:ちょうど私自身が代表になったのは、2020年ですが、まさにコロナ禍のタイミングでした。一気に世の中の雰囲気は変わりましたよね。まさに織物、着物において不要不急に捉えられる面もあったと思います。しかし、本当にそうなのかと。昔も飢饉などはあった中で、美というものは残ってきていることから、西陣のことも含めて、自分たちのDNAがどこにあるのか考えたときから、これまでやってきたことを再定義するようになりました。
その中でも、「協業」が重要だと感じています。協業から美が生まれ、協業から革新が生まれます。コンピュータプログラマーや数学者、海外アーティストとの協業により、今の時代しか実現できない織物や作品が生まれると考えています。もちろん、僕らを知らない人に知ってもらうためにはまだまだ道半ばではあります。西陣が海外で本格的にスタートしたのは2010年ですから、まだまだ始まったばかりだと感じています。
加藤:「The Mind Landscape(*7)」はイタリアの著名建築家でありデザイナーであるミケーレ・デ・ルッキが率いるスタジオAMDL CIRCLEとHOSOOの協業により生まれたコレクションですが、ミケーレ・デ・ルッキの「自然の驚異的な力と人間のはかない本質の間に立っている」建築家としての視点がテキスタイルとも共鳴した素晴らしいインスタレーションでもあると感じました。ミケーレ・デ・ルッキとはどのようなきっかけで協業されたのですか。
細尾:去年、僕らはミラノのブレラという地域でショールームをオープンしました。ブレラは17世紀に建てられた歴史的な建物の中にあります。ミケーレ・デ・ルッキ氏は前々から存じ上げていましたが、建築のみならず思想や哲学が素晴らしいと思っていました。ミラノのショールームがミケーレ・デ・ルッキのスタジオの近くだったんです。そういうご縁もあり、ショールームにきていただいたのがきっかけです。ミケーレ・デ・ルッキ氏は早い段階から、自然と人との共生をテーマにしていましたし、職人の工芸性やものづくりを重要視しています。だからこそ、セッションしたら、一体どんな織物ができるんだろうと思っていました。
The Mind Landscapeというシリーズは、基本的には「ミクロ、マクロ、人」という3つの視点で構成されています。1つ目は織物のパターンは「マクロな視点」で顕微鏡で木を覗いたときの細胞、2つ目は「ミクロの視点」で地球の外から地球や森をみたときの衛星写真です。このようなミクロとマクロの2つの視点を一つの織物の内に調和させました。さらに3つ目は、「職人の視点」によって初めて織物ができるという人の視点をコンセプトにしています。僕らも、並行して、人と自然の関わりなどについてリサーチをしていきました。
加藤:先ほどの話で織物とアーキテクチャという視点がありましたが、建築とテキスタイルという異なる領域を合わせたのはどのような意図があるのでしょう。
細尾:建築と織物は非常に似ています。織物もアーキテクチャです。また、織物には構造計算が必要です。経糸と緯糸の絶妙な均衡関係を捉えることでつくられます。柔らかいもの、身体に近いものではありますが、環境と人との間に在るものは、実は建築と非常に似ていると捉えています。
小川:実は空間的な構造体である織物を建築とコラボレーションさせることによって、改めて、その本質を浮かび上がらせたというのが、The Mind Landscapeというコレクションでもあるのだと、改めて、理解が深まりました。コレクションの布が1枚そこに佇むだけで、森の奥深くにつながっているかのような、不思議な錯覚と言いますか、非常に空間的な世界観を観せていただいたような感覚になりながら、コレクションを拝見していました。
細尾:織物は3Dです。遊牧民のゲルなど織物の建築物もあります。2016年に遊牧民族と共同生活をしたことがあります。ゲルは枠を木、外側は帆布で、内側は断熱材としてのフェルト、織物の装飾で構築されている 織物の建築です。そのような意味では、コンクリートなのか、木なのか、木綿なのかという素材の違いだけですね。
加藤:では、最後に、文化的な側面から社会と接続した新しいアプローチをしていく文化起業家やデザイナー、新たな領域で未来に挑戦する若き起業家の方々に対して、革新していくためのメッセージをお願いします。
細尾:文化や伝統を繋いでいくことは絶対一人の世代にはできないです。いかに挑戦してまたこのバトンを繋ぐか、また次の世代の人たちがバトンを受け継いで、挑戦して、また、次の世代にバトンを繋ぐ。
伝統を守るためにはもう、攻め続けて革新し続けないと守れません。もちろん、その中で変わらない部分があります。革新した中で残ったものは変えてはならない部分であって、常識や固定観念で決めてしまうと、そこにのみ込まれてしまう。 だからこそ、挑戦し続けています。
加藤:バトンを渡し続けていくことで、美という伝統が継承され、革新の連続が生まれてくるということですね。本日は大変貴重なお話をありがとうございました。
*7 The Mind Landscape:ミラノデザインウィークにて発表されたHOSOOの新作テキスタイル・コレクション「The Mind Landscape」を紹介した展覧会。イタリアの著名な建築家でありデザイナーであるミケーレ・デ・ルッキ率いるスタジオAMDL CIRCLEとHOSOOの協業のもと制作された。
index











contents
© Loftwork Inc. All rights reserved
index











contents
© Loftwork Inc. All rights reserved