
© DYNAMIC EQUILIBRIUM OF LIFE / EXPO2025
Interview
創造的進化とは、何か?
生物学者・作家
福岡伸一さん
京都大学卒および同大学院博士課程修了。ハーバード大学研修員、京都大学助教授などを経て、現在、青山学院大学教授・米国ロックフェラー大学客員教授。サントリー学芸賞を受賞し、90万部を超えるベストセラーとなった「生物と無生物のあいだ」(講談社現代新書)、「動的平衡」シリーズ(木楽舎)など、“生命とは何か”を動的平衡論から問い直した著作を数多く発表している。また、大のフェルメール好きとしても知られ、最新のデジタル印刷技術によってリ・クリエイト(再創造)したフェルメール全作品を展示する「フェルメール・センター銀座」の監修および、館長もつとめた。2025年の大阪・関西万博で、テーマ事業「いのちを知る」を担当。
小川敦子(以下、小川):福岡先生、初めまして。今日はよろしくお願いします。
ロフトワークは、25年前の創業時から、一人ひとりの創造性を活かし合い越境し合うような“多様性”を前提としたチーム醸成を図り、企業や地方自治体や国など様々な領域のクライアントの方々と共に新たな価値や変容を生みだすプロジェクトをこれまで手掛けてきました。企業、自治体、あるいは、社会という単位においても『生態系=エコシステム』として捉えることをその前提としながら、共通の価値や認識や言葉という“コモンズバリュー”を共にデザインし、社会へ開いていくことをあらゆる事業の軸にしています。これまでは、主にビジネス領域において共に進化することにトライしてきましたが、これからは都市、社会というフィールドに領域を拡げて、さらに多様な方々と共に進化を考えていきたいというのが、共に在る社会=Aru Societyプロジェクトのコンセプトです。
福岡先生と坂本龍一さんの書籍 『音楽と生命(坂本龍一、福岡伸一共著、(株)集英社2023年発行)』を拝読させていただきました。何度も読み返しながら、一字一句理解を深めようとしていますが、読むたびに発見がありますね。自然の摂理、この本では、そのような本来的な自然を“ピュシス”という表現をなされていますが、自然の側からあらゆる事象を捉え直すように物の見方を変えていくと、これまで当たり前だと思っていたこと、ものの見方や考え方そのものがリセットされていくような感覚を覚えました。それと同時に、この著書で描かれている本来的な進化の捉え方は弊社が重視してきた“コモンズ”という考え方とも根底では非常にリンクすることが多いような印象を勝手ながら受けています。
福岡先生は、自然(ピュシス)をありのままに記述する言葉(ロゴス)であり、より解像度の高い表現こそが重要であると著書の中で説かれていますが、改めて、なぜ自然(ピュシス)の豊かさを回復することが重要だと思われるのか、その背景のお考えについて、ぜひお聞かせください。
“自然(ピュシス)の豊かさを回復する” 新たな思考を体験する万博パビリオン
福岡伸一(以下、福岡):ありがとうございます。
まず、具体的な話からする方がわかりやすいかなと思うのですが、今、私は2025年日本国際博覧会(略称「大阪・関西万博」)というイベントのテーマ事業と呼ばれる企画のプロデューサーの一人を拝命しております。この万博のテーマが「いのち輝く未来社会のデザイン」とされています。ここで、改めていのちを考えるというのが、この万博のテーマなんですね。テーマ事業のプロデューサーというのは、自分の考えに基づいてパビリオンをつくり、その中で何らかの展示をやる。建築やデザイン、あるいはビジョン、哲学を示すことが課せられた役割です。私は「いのち動的平衡館」というパビリオンをつくっています。建物は全体として、ふわりと細胞膜が地上に降り立ったような、ドーム状の形状をしております。
1970年に大阪万博があって、その時のテーマ館には岡本太郎が作った太陽の塔というものがあり、今も残っているわけです。あの時は「人類の進歩と調和」がテーマだったんですけれど、岡本太郎は人類は調和もしていないし進歩もしていないじゃないかということで、アンチテーゼとして縄文的な太陽の塔を建てたんですね。その岡本太郎の叫びと言いますか、意思を受け継いで、我々は新しくもう一度、いのちについて考えてみようと。
館の外観は、一枚の薄い膜が降り立ったような構造で、一柱が一本もなく、自分の力で立ち上がっている非常に自律的な建物です。我々がどこから来てどこへ行くのか? 生命とは何か? 生きているとはどういうことか? 生命の進化とはどういうことなのか? といったことを捉えようとしているわけですね。ここに私の生命哲学や坂本さんと語り合ったピュシスとロゴスの問題について議論したことをすべて投入しています。
しかし、限られた時間や展示スペースであまり難しい説明をしても万博のパビリオンとして楽しくないので、大人にも子どもにも分かりやすい展示方法を考えています。建物の内部には、「クラスラ」と名付けられた50万個もの立体LEDによって光の粒を描き出すシアターを作りました。それを使って、ここに「生命の物語」を再現しようとしています。
まず、はじめに、私たちはどこからきたのか?について、考えていきましょう。
自分の身体は自分のものであると通常は捉えていると思いますが、私たちの生命というのは38億年の生命の流れの中からやってきているわけです。いのち動的平衡館では、自分の身体の粒子が溶け出して大きな流れの中に合流し、生命のはじまりである一番最初に地球上に現れた初源的な細胞に戻ります。そこから進化のドラマが再現されて、現在の私たちに至るまでの38億年分のドラマを15分ぐらいで観せていきます。 “動的平衡”という生命哲学を、言葉ではなく体験として直感的に伝える展示を目指しました。

© DYNAMIC EQUILIBRIUM OF LIFE / EXPO2025
生命は“利他的な”革命によって、進化を遂げてきた
20世紀型のパラダイムですと、リチャード・ドーキンスが唱えた「利己的遺伝子論」というものがあります。我々生命体は遺伝子の乗り物であって、遺伝子とは単一の目的のためだけに生きているわけですね。単一の目的というのは自己増殖をするということです。遺伝子は自己増殖をするために非常に利己的に振舞ってきた、それが進化の大きな流れであると唱えているのが利己的遺伝子論なんです。確かに、適者生存のような進化の物語をそういう見方で見ると、より環境に適応して、より自分の子孫を残せる生物が生き残っている。遺伝子の視点から見ると非常に利己的に振る舞ってきたことによって現代の人間まで進化してきているように見えるというわけですね。
しかし、この20世紀型のパラダイムというのは少し古びてきているし、一元的すぎる見方なわけですね。生命の歴史を眺め渡してみると、ダイナミックな進化のジャンプが何回か起きています。一見すると、突然変異が起きて、その中で環境に適合するものが選び抜かれて生き残ったように見える側面ももちろんあるんですけれども、それだけではない。利己的ではなく、生命が「利他的に」振舞ったときこそ、生命は大きく進化しているんです。
この「利他」という言葉がキーワードなんです。生命38億年の歴史の中では、3回程度、利他的な革命があります。
第一は、単純な細胞が複雑な細胞になったこと。難しい言葉で言うと、原核細胞が真核細胞に進化したというイベントがあったんですね。単純な一枚の袋でとり囲まれている細胞の中に、ミトコンドリアとか、葉緑体とか、細胞角とか、細胞内小機関と呼ばれる複雑な仕組みができたのです。この進化によって生命は大きく前進しました。しかし、これは遺伝子が利己的に振舞ったからではないし、突然変異で急にこのような複雑なことが起こったわけでもないのです。大きい細胞と小さい細胞が出会って、普通だったら大きい細胞が小さい細胞を食べて栄養にしてしまっていたのを、そういう一方的な食う・食われるという関係性を、共生的な関係・利他的な関係に組み変えたんですね。大きい細胞は小さい細胞を取り込むけれども、それを細胞の中で破壊するのではなく、小さい細胞が大きい細胞の中の環境で守られながら、大きい細胞の中で増殖できるようにして、小さい細胞は得意なこと、エネルギー生産だったらエネルギー生産、太陽光線の補填であれば光合成という役割を担う。細胞の中にもう一つ小宇宙を作って、大きい細胞と小さい細胞が共存、共生するようなことが起こったので細胞が複雑化できた。これが第一の利他的な革命です。
第二の利他的な革命は、バラバラに存在していた単細胞生物が集合して、役割分担をして、より大きな多細胞生物を作ろうとしたときです。単に競争していたのではなく、得意なことを持ち寄るという利他的な共生によって、単細胞が多細胞化して、多細胞化することによってより大きな生命をつくることができる。この進化によって、今日の生命の多様性、ひいては人間のような多細胞生物を創り出すことができるようになったわけですね。
さらに、第三の利他的なジャンプ、革命が起こります。単純に細胞分裂で自分のコピーを再生産するクローン生殖(無性生殖)が主流だったところにオスとメスという性をつくって、その二つが協力しないと新しい生命が作れないという面倒くさい仕組みをつくったのです。しかし、そのことによって遺伝子をより積極的に交換・混合することができ、より新しい変化、生命の多様性を生み出したということなんですね。ここでも、オスとメスという不完全な存在が互いに他を必要として支える利他の関係があります。
このように考えていくと、利己的遺伝子論は利他的な共生論として書き直されるべきだと感じます。生態系全体の見方、地球環境全体を弱肉強食や優勝劣敗のような競争・闘争の歴史として見るのではなく、共生、利他性の歴史で見ていく。このような共生、利他性の生命観が「動的平衡の生命観」であり、「いのち動的平衡館」ではこれを来場者の皆さんと一緒に考えようとしていています。
また、生命は時間というものを持っていて、それは有限です。我々はどこからきているのか? というと、今お話ししたような38億年の生命の利他生の流れからきているわけですが、私たちはどこへいくのか? ということについて考えると、「死」という問題を避けて通れないわけです。死というのは一般的には遠ざけたいもの。なるべくなら考えたくないもの、あるいは恐ろしいもの、悲しいものとして捉えられていますけれども、これまた生命全体の流れを見るとですね、死ぬことというのは新しい生命に時間、場所、資源を手渡すということなのです。つまり、死は最大の利他的な行為とも言えるわけです。
いのち動的平衡館では、こういった生命の利他性を中心に、動的平衡の生命観をもう一度みんなで考えようというフィロソフィーを提案しようとしているわけなんです。はじめのご質問に戻りますが、ピュシスの豊かさというのは、つまり、生命の持っている利他性に気がつくということだ、と言い換えることができるのではないでしょうか。
小川:生命の壮大な流れの中に、利他性というものが在る、私たち自身の生命が一連の流れとして感じることができるというのは、非常に心が豊かになりますね。パビリオンを訪れるのが非常に楽しみです。ところで、このAru Societyプロジェクトのアドバイザーにも入っていただいている住田孝之さんという方が経産省時代に、万博の「いのち輝く未来社会のデザイン」というタイトルを名付けたと伺っています。当時、本当は “生命” という言葉をタイトルの頭に付けたかったこと、人間中心の目線ではなく、自然、つまり生命全体の総体的な考えから、このタイトルを考えたと仰っていました。
福岡:万博とは、歴史的には技術や新しい考え方によって新たな価値を生み出す産業振興も含めたイノベーション・テクノロジーのお祭りなので、70年万博の時も動く歩道や携帯電話の原型が展示されて、みんなが驚きました。今回も、新しいテクノロジーを見せるという側面、それが万博の主流の意義でもあります。
ただし、現代は新しいテクノロジーはこういうお祭りや催事で初めて見せなくても、ネット上にどんどん展開されているわけなので、もう少し新しい万博の意義が必要なんじゃないかということで、2025年の万博では、生命哲学や社会の新しいビジョンを考える場にしたいというのが、一つのコンセプトです。私は、その辺りを担当すべく頑張ってきました。
小川:素晴らしいですね。「生命とは何か?」という本質的な観点が盛り込まれた、普遍的な新たな社会ビジョンが生まれてくるであろうことを願っております。
では、次に先生にお伺いさせていただきたいテーマは「創造的進化」についてです。人間はどのような時代においても、挑戦すること、変化することを恐れずに何とか生き残り続けていく生き物でもあると思います。一方で、そのような進化が、気候変動、パンデミック、戦争など、あらゆる事象を起こし、ロゴス的なものの見方、人間中心のものの見方、考え方がさらなる変化を起こそうとしているのも、また事実ではあると思います。ご著書の中では、フランスの哲学者アンリ・ベルクソンの「創造的進化」の解釈をベースとしながら、動的平衡による先生独自の生命観について説かれていますが、より良い未来を創造するためにも、アンリ・ベルクソンが提唱する考え方を私たちはどのように捉えると良いのか、ご教示いただけますでしょうか。おそらく、創造的進化の真意を捉え直すことはイノベーションという変革の真意を問い直すことでもあると考えております。先生のお考えを是非お聞かせください。
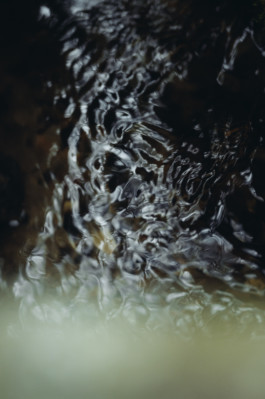
自然(ピュシス)の利他的な在り方、振る舞いを
人間はロゴス(言葉)の力によって取り戻すべき時にある
福岡:自然は、そもそもが競争や闘争をしているのではなく協力している、つまり、利他性によって支えられている状態です。これが、本来のピュシスの在り方なんですね。今お話したような進化のプロセスにおいても利他性が中心原理になっていますし、現在の地球環境でも、利他性はたくさんのところに見えてきます。
一番利他的に振舞ってくれているのが植物で、植物は太陽光線のエネルギーを光合成という作用によって有機物に変えてくれているわけですね。しかも植物は必要以上の量を作り、その余剰分をため込まずに他の生命に手渡してきました。もし植物が自分たちの生存に必要な分だけしか有機物を作っていなければ、つまり利己的に振る舞っていたら、他の生物が進化する余地はゼロでした。
植物が利他的に振る舞って、過剰に光合成をして、葉っぱを茂らせて、それを虫や鳥に食べさせ、葉が落ちて土壌を豊かにしてくれているわけですし、木の実や果物、穀物、お芋などは基本的に自分のためにエネルギーを作っているんですが、それをある意味惜しげもなく他の生物に与えてくれているわけですよね。それが草食動物を支え、あるいは昆虫を支え、また昆虫は花粉を媒介するような遠方的な働きを果たし、草食動物は動物性、肉食動物の餌になり、あらゆる動物はまた分解されて植物の栄養になったり、二酸化炭素になったりして地球環境が回っているという、自然本来のあり方、ピュシスの在り方とは利他性なわけです。
その中で人間だけが利己的に振舞っているのです。人間は自分が地球上で一番偉いと思っているし、自分が地球の支配者で、他の資源はみんな人間のためにあるというふうに思っている。地下に眠っていた自然資源の石油や石炭、天然ガスを掘り出してどんどん燃やして、二酸化炭素を空気中に増やしてきました。それを戻すのは本来植物の作用だったのですが、熱帯雨林を開発し、都市をつくり、植物をどんどん減らしているので、二酸化炭素の量が地球上に増えてしまっているというのが環境問題です。二酸化炭素そのものは悪者でもないし毒でもない。循環の一形態として、二酸化炭素が滞留していることが問題なのです。
人間だけが自然本来の在り方、利他的に振る舞うべき生命の在り方を忘れて、利己的に振舞ってしまっているのが現代社会です。そして、それを推進しているのが資本主義というものだとすると、そこを見直さないとならない。では、どうして人間だけが利己的に振る舞うようになったのでしょうか? 人間だけが、他の生物と違う文明を創り、テクノロジーを駆使し、あるいは、社会制度を創ったり経済を創ったり、貨幣を創ったりしています。
他の生物は基本的に富を蓄積していないわけです。もし過剰にあれば、それを必ず誰かに手渡している。なぜかというと、取っておいても仕方がないからです。何か資源を貯蓄しても、それは腐るかダメになるかなので、あらゆる生物は何かを過剰に生み出したり、得たときには、必ずそれを他者に手渡している。それが利他性です。植物ほどではなくとも、他の生物も多かれ少なかれ利他的に振る舞っているのに、人間だけが利己的に振る舞って、富を貯蓄し、私有財産を増やしてきました。
では、なぜ人間だけがピュシスの原則から外れて利己的に振舞っているのかというと、それは端的にいうと、ロゴスのせいなんですね。つまり、人間だけが言語を創り出し、言語の作用によって世界を構造化して、さまざまな社会システムを創り出しました。文明や、経済や、法律や、貨幣や、それらはすべてロゴスの産物なんです。言語には、コミュニケーションの道具としての側面があり、それは他の生物にも同様に存在します。鳥が鳴いたり、昆虫が羽を擦り合わせて歌を歌ったりというように、多くは求愛行動としてのコミュニケーションのツールとしての言語があるんです。
しかし人間は、コミュニケーションツールだけではなく、世界を構造化する、フィクションを創造するための道具として言語を用いたわけですね。このことによって文明ができ、経済ができ、社会制度や基本的人権を創り出せた。一人ひとりが生きている意味があり価値があるというのが基本的人権ですよね。それを保証しているのは、全てロゴス、言葉なんですね。男だろうが女だろうが、大人だろうが子供だろうが、障害を持った人や病気の人にも、それぞれ基本的人権があって生きる意味があり価値があるということを互いに約束できたのはロゴスの作用なので、人間が生み出したロゴスというのは素晴らしいものであるのは間違いがないわけです。
他の生物はロゴスを持っていないので、個々のいのちというのは自分で生きることができなくなればそれで終わりだし、何万個の卵を産んでもその卵一つ一つのいのちはそれほど重みを持たずに、他の生物に食べられたり流されたりしてしまうという、ピュシスの持っている残酷な側面というものがあるわけです。
人間だけが、ロゴスを作ったおかげで、個々のいのちに等しく価値があるという基本的人権の概念を生み出しました。本来のピュシスは素晴らしいんですけれど、残酷な側面を持っています。人間はロゴス的な言葉の作用によってピュシスの本来の残酷さから逃れて、個々の生命の価値を作り出したのです。
ただ、ロゴスには非常に負の側面というか、行き過ぎるとよくない側面があって、ピュシスを分節する力、切り分ける力があるのです。本来の自然は動的平衡の流れの中に、利他性の中にあって、それはあらゆるものが相互に繋がっているというのが本来のピュシスの在り方ですよね。
でもロゴスというのは、そういったある種の混沌とした自然を言葉の作用によって切り分けて、概念化して、整理して、その上に文化や文明を作っているわけです。それが非常に人間を人間たらしめていることではあるのですが……。例えば、ロゴスの作用で海とか川とか湖とか雨とか雪とか、水の流れを分節していますよね。河川だったら、国交相管轄で、海だったら水産庁管轄というふうに、管轄まで分節化されている。でも本当は、水の流れは一体的なものだし、海も川も雨も雪も、あるいは我々の身体の中を通り抜けていく水も本来は一連の流れなんですが、ロゴスの作用によって切り分けられて個別なものとして概念化されると、本来の有機的なつながり、動的平衡としてのつながりが見えなくなってしまう。ピュシスの動的な作用がロゴスによって分断されてしまう。
だからこそ、人間はロゴスを捨てることはできないけれど、ロゴスによって切り分けられすぎた、機械論的に見做されすぎたピュシスの在り方を回復することが大事なのです。そして、それもまた、ロゴスの、言葉の力によってしか回復できないのです。ピュシスをありのまま、ピュシスとして受け入れるのが良いとすると、人間はロゴスを手放して昔の動物世界に戻らざるを得ないですが、そんなことはできないですよね。人間がロゴスを持った特別な生物としてやらなければならないのは、切り分けられすぎたロゴスの作用というものに気がついて、その上で利己的になりすぎた人間の在り方を反省して、本来のピュシスの在り方を、新しい解像度の高いロゴス、言葉によって説明し直す。概念として取り戻すのが、今、我々が行わなければいけないことなんじゃないかなというのが、私の生命哲学なんです。
小川:ありがとうございます。生命の利他的な振る舞いの在り方へと立ち返ること、そこがまずは出発点となりそうですね。さらに、それを言葉によって表現し、人間の振る舞いという所作という新たな共通の認識を持つことが大切になってきますね。

常に自己破壊を繰り返しながら、つくり直すという生命の在り方
創造的進化の意義は、落ちていく坂を登り返す “努力” という営みにこそある
福岡:では、ここから、ご質問をいただいたベルクソンの創造的進化についてお話をしていきたいと思います。
動的平衡とは、あらゆるものが相互に繋がっているということを意味します。そして、絶えず物質もエネルギーも環境からやってきて、一瞬、我々の生命を形作るんですけれども、それはまた環境に放出されていって、大きな循環の中で覚醒酩酊があり、このように常に動的なものです。その動的な循環を回すために我々は何をしているのかというと、常に自己破壊をしていて、そしてまたつくり直すということをしているわけですね。だから、常に壊しながらつくり直すということを生命はしている。これもまた動的平衡のコンセプトの大事な部分です。
生命とAIというテーマで言いますと、AIがそのうち人間を凌駕してシンギュラリティを越えると、生命的なものになって人間を支配するんじゃないかと恐れられていますけれども、AIにできないことが一つあって、それは、自己を破壊しながら新しくつくり直すことですよね。AIは常にデータを溜めていく。履歴を増やしていって、その履歴の中から最適な解を選び出すということしかできない。でも、人間を含めた生命は常に自分を壊してつくり直すことができます。
百年前のフランスの哲学者アンリ・ベルクソンは、この生命の特性を「生命というのは物質が下る坂を上り返すような努力をしている」というふうに、自身の著書『創造的進化』の中で言いました。生命の持っている壊す作用というのは、まるで落ちていく坂を上り返すような努力だと、彼は見たわけです。これは非常に慧眼だったのですが、生命の原理について充分な知見が科学界からはまだなかった時期の言葉なので、哲学者の言葉として止まってます。もう少しこれを科学的な言葉で言い直すと、物質が下る坂というのは何かというと、「エントロピー増大の法則」によって説明ができます。エントロピー増大の法則は宇宙の大原則で、秩序のあるものは秩序のない方向にしか動かない。形あるものは形が崩れていく方向にしか動かない。時間の経過とはそういうもので、どんな壮麗なピラミッドのような立派な建造物でも、出来立てはピカピカですけれども、長い年月のあかにだんだん劣化して風化して砂粒に戻っていく。これがエントロピー増大の法則です。
整理整頓していた机や部屋も、ちょっと油断するとすぐに散らかったりゴミが溜まってしまったりする。これもエントロピー増大の法則です。あるいは淹れたてのコーヒーは熱いけれど、すぐにぬるくなってしまうのも、熱が拡散するということでエントロピー増大の法則ですよね。これが物質が下る坂で、放っておくと物質はエントロピー増大の法則に翻弄されながら、だんだん秩序をなくしていく。でも生命体だけはその坂をなんとか登ろうとする努力があるというふうに、ベルクソンは言っているわけです。確かに、細胞はすごく秩序が高いシステムですが、細胞膜は常に酸化されてしまう。活性酸素が降り注いできてどんどん錆びついてしまう。それから細胞の中には老廃物が溜まって、あるいはタンパク質の片生物が溜まっていったりします。放っておいたら生物もだんだんエントロピー増大の法則によって坂を転がり落ちてしまうんですけれども、生命体はそう簡単にエントロピー増大の坂を転がり落ちずに、その坂を必死に登り返そうとしているわけですね。
ベルクソンは、どうして上り返せるのかということを解き明かすことはできなかったのですが、私の提唱する動的平衡論では、それをこう解釈しています。
生命は自分自身を率先して破壊している。エントロピー増大の法則よりも速い速度で自らを壊している。壊すことによってエントロピーをどんどん捨てながら、新しくつくり直すことで、エントロピー増大の坂を登り返す営みをしているのです。それを“努力”とベルクソンは呼んだわけですが、まさに生命が持っているある種の健気さ、一生懸命さをいのちの輝きだとすれば、“いのち輝く” ということは、この坂を一生懸命登り返そうとしている、その営みにこそあると言えるわけですね。
しかし、生命はエントロピー増大の法則に一時的に抗うことはできても、ずっと勝ち続けることはできず、やがては、ずるずるとその坂を落ちていかざるを得ません。登り返そうとしているが、少しずつ後退していく。これが老化ということであり、最終的にはエントロピー増大の法則に打ち負かされるということは、つまり “死” を意味します。先ほども申し上げたように、死は個体としての生命の終わりですけれども、動的平衡の大きな流れの中では次の生命に引き継がれるので、死もまたバトンタッチであり利他的行為であると言えます。なので、創造的進化というベルクソンの言ったことのなかで一番大事なのは、壊しながら進んでいるということ。それは、動的平衡論のキーコンセプトでもあるわけです。
小川:先生の説明はとてもわかりやすいですね。何度もベルクソンの創造的進化の理論的な理解に努めようとしても、1日2ページぐらいしか読み進めることが出来ないほどに難解でしたが、先生の説明でよく理解できました。このような創造的進化のお話と利他性という本来の生命、生態系の在り方のお話は、非常に密接に絡んでいるのですね。
福岡:壊しながら、つくり直しているというのが地球環境本来の生態系であり、本来の生態系とは利他性というものを大切にしているので、人間が利己的に振る舞いすぎていることを反省するべきですね。威張るな人間!ということです。人間もエコシステムの一員であるならば、生命本来の動的平衡、そして利他的に振る舞うということをもう少し考え直さなければならない。利己的に振舞っていると、地球環境全体を損ねてしまって、それは結局人間にリベンジすることになるわけです。人間にとっては地球環境はなくてはならないことですけれども、地球環境にとっては人間はなくていいわけですから。そこを人間という生物は見誤ってはいけないということですね。
小川:本当にそう思います。謙虚さというものについて、自然、生命の在り方から私たちは学び直すべきときにありますね。
最後の質問になります。“シグナルとして取り出されたものではない、本来のノイズとしてのピュシスの場所に下りていくためには、客観的な観察者であることをいったんやめて、ピュシスのノイズの中に内部観察者として入っていかないといけいない。それはある意味で、非常にパーソナルな体験である。”(著書:音楽と生命(坂本龍一、福岡伸一共著、(株)集英社2023年発行))というご発言の記載がありました。これは、まさに、日本が培ってきた精神性や文化、芸術とも、深く繋がるものがあるのではないかと感じていますし、この感性を取り戻していくことは、関係を細分化し断ち切っていく、いわば、ロゴス的な考えのもと構築された、今の社会のありようへの違和感と変容をもたらすことができるかもしれないと考えます。また、このような考え方をロゴス、つまり、「共通言語 common language」として意味づけをし、日本、世界へと伝えていくことも、とても大事なことであると思います。改めて、自然(ピュシス)という豊かさを回復することをどのように表現することが望ましいとお考えでしょうか。

破壊的創造。イノベーションの本質は
ロゴスから、ピュシスへと立ち返るプロセスにこそ見出すことができる
福岡:地球環境にピュシスという言葉を当てはめると、利他性、動的平衡の関係性が成り立ち、あらゆるものが相互に繋がっている動的なものとして捉えることができます。それを人間のロゴスが分節化しすぎている。このロゴス的な捉え方を見直していかないといけない、というお話をしてきました。これは、坂本さんとの対談の中でも繰り返し語っていることです。坂本さんご自身も、最初はYMOの電子音楽のように、音楽というものをデジタル化して音符を分節化し、非常に再現性よく織り出すというところに面白さを感じて、一世を風靡しましたが、その後、やっぱりロゴス的に行き過ぎるというのは本来の音楽を追求する行為ではないと、だんだん自然音とかノイズとか、不協和音とか、デジタル音楽はシンクロナイズドミュージックですけれど、そうではない “アシンク” というところに回帰していきましたよね。
私もまた生物学者として、最初は遺伝子を一生懸命研究していたわけです。遺伝子というのは、ある意味生命のデジタル情報なので、遺伝子を解析するとデジタル暗号が読み解けて、生命のミクロなメカニズムがわかってくるわけですけれど、生命を情報化しすぎると、あるいはメカニズムとして捉えすぎると、生命の持っている本来の動的なもの、つながり、利他性、ピュシスというものを見失ってしまいます。私自身も、坂本さんがデジタルから自然音に戻ったように、分子生物学のデジタル的な遺伝子万能論というところから、もう少し統合的な生命論を打ち立てるべきだというふうに、自分の中でのパラダイムシフトとして、動的平衡論というものにシフトしていったわけです。
だから、坂本さんと私は音楽家と生物学者という全然違うフィールドで活動していて、本来はご縁がなかったはずなんですけれども、お話をする機会があり、だんだん意気投合していく中で同じことを考えているのだな、ということを相互に分かってきました。人生のプロセスは、少年時代はピュシスとして生きていても、勉強していくというのはロゴス化されていくということです。その中で、彼は音を切り分けていくという音楽理論にデジタル音楽の方向に、私は生命を切り分けてミクロな解析をする、遺伝子を解析するという方法のデジタル的なものに最初は行きました。それは、人間が何かを学ぶ、勉強するということは基本的にはロゴス的に物事を究明するということなので仕方がないプロセスなんですが、ロゴス的なところに行き過ぎると、本来的なピュシスを見失ってしまうということで、ある時点でピュシスに回帰して行っているというのが、二人の同じような人生の航路なわけですよね。同じだったから、馬が合うというふうにも考えられるんではないかなと。
「ロゴスから、ピュシスへ」という旅路は誰もがありうることです。それぞれ一人ひとり、このモデルを考え直されてみてもいいんじゃないかなと思うわけです。一人ひとりが立ち返っていくことの重要性はそういうところにあるんじゃないかと思います。
小川:ロゴスから、ピュシスへとそれぞれが自ら壊しながら、またつくり直していくということ。その行為自体がピュシスの本質に返っていくということでもあるのでしょうか?
福岡:いきなりピュシスのところに行くとですね、宇宙は全部繋がっているみたいな、ちょっとスピリチュアルな感じになってしまうんです。私と坂本さんがそれなりに頑張ってきたと思うのは、一度はロゴス的な方法での究極を見極めた上で、それだけでは世界を十分説明しきれないから、ピュシスの本来の在り方はそうではないということに気がついて、その反省の上に、逆に戻ってきたことです。そういう過程が必要なんじゃないかなと思うわけですね。
小川:そうですね。一度は坂を登り切ってから立ち返るということのゆらぎこそが重要な観点だということですよね。今は社会も世界も、大きなパラダイムシフトを迎えている、いわば転換期にある。今、企業も本来は自然の摂理と同じように常につくり直しながら、落ちていく坂を登り返していく活動そのものがなければ、生き残っていくことが難しくなる時代に置かれていると感じています。企業の活動というところにもこのようなお話を置き換えて、お話をしていけるといいなと思いました。まさに利他性という共に在ることを考えていくことを、私たち自身の役割としてやらないといけないなと改めて感じています。
福岡:今日私がお話ししたことをうまくトランスレートしていただけたらいいなと思います。どんなお仕事をしている方も本来の自然とそれを切り分けていくロゴスのジレンマみたいなものがあるはずです。地球環境に本当に適ったものがピュシスですが、そうすると企業活動というのは究極のロゴス活動ですから、そこに相反があるというのは確かなのですよね。いかにその二つを往復しながら新たな道を見つけていけるかというのが21世紀の課題だと思いますし、社会や環境のことを配慮しながら、経済活動をしましょうということです。ロゴス、つまり利潤追求ということだけ求めていると企業もロゴス化していくということですよね。地球本来の在り方とピュシスをどう回復していくのかということが課題となっているし、それが万博のテーマでもあります。御社が考えておられるようなAruSocietyの目標とも重なってくるんじゃないかと思います。
小川:私たちがやるべきなのは、利潤の最大化ではなく「価値の最大化」というところなのかなというのは考えています。価値の最大化について考えていくと、常につくっては壊しというのが繰り返されるうちに、どんどん価値がアップデートされていくということですものね。
福岡:動的平衡であり、ベルクソンがいう創造的進化の中の破壊という話は、壊れたから取り替えるとか、古くなったから交換するという意味の新陳代謝じゃないんですよね。出来立てほやほやでも、まだまだ使えるにも関わらず、どんどん壊していくというのが動的平衡の破壊だし、実際に細胞の中で起きている破壊も同じです。つまり、率先してどんどん破壊しているわけです。そうしないと、エントロピー増大の法則に打ち勝って、転がる坂を登り返すように生きていけない。単なる破壊じゃなくて、破壊的創造と言うか。
小川:先生のお話を根底に置いて、企業のイノベーションの本質を捉え直してみると、創造的進化の捉え方、利他性という自然の在り方、私たちは常に破壊しながら創造していくという動的な動きをあらゆる状況で回復させていくことの先に、次の時代の社会の在り方が見えてくるのではないかと改めて感じることができました。福岡先生、今日は本当にありがとうございました。
Interview

© DYNAMIC EQUILIBRIUM OF LIFE / EXPO2025
創造的進化とは、何か?
生物学者・作家
福岡伸一さん
京都大学卒および同大学院博士課程修了。ハーバード大学研修員、京都大学助教授などを経て、現在、青山学院大学教授・米国ロックフェラー大学客員教授。サントリー学芸賞を受賞し、90万部を超えるベストセラーとなった「生物と無生物のあいだ」(講談社現代新書)、「動的平衡」シリーズ(木楽舎)など、“生命とは何か”を動的平衡論から問い直した著作を数多く発表している。また、大のフェルメール好きとしても知られ、最新のデジタル印刷技術によってリ・クリエイト(再創造)したフェルメール全作品を展示する「フェルメール・センター銀座」の監修および、館長もつとめた。2025年の大阪・関西万博で、テーマ事業「いのちを知る」を担当。
小川敦子(以下、小川):福岡先生、初めまして。今日はよろしくお願いします。
ロフトワークは、25年前の創業時から、一人ひとりの創造性を活かし合い越境し合うような“多様性”を前提としたチーム醸成を図り、企業や地方自治体や国など様々な領域のクライアントの方々と共に新たな価値や変容を生みだすプロジェクトをこれまで手掛けてきました。企業、自治体、あるいは、社会という単位においても『生態系=エコシステム』として捉えることをその前提としながら、共通の価値や認識や言葉という“コモンズバリュー”を共にデザインし、社会へ開いていくことをあらゆる事業の軸にしています。これまでは、主にビジネス領域において共に進化することにトライしてきましたが、これからは都市、社会というフィールドに領域を拡げて、さらに多様な方々と共に進化を考えていきたいというのが、共に在る社会=Aru Societyプロジェクトのコンセプトです。
福岡先生と坂本龍一さんの書籍 『音楽と生命(坂本龍一、福岡伸一共著、(株)集英社2023年発行)』を拝読させていただきました。何度も読み返しながら、一字一句理解を深めようとしていますが、読むたびに発見がありますね。自然の摂理、この本では、そのような本来的な自然を“ピュシス”という表現をなされていますが、自然の側からあらゆる事象を捉え直すように物の見方を変えていくと、これまで当たり前だと思っていたこと、ものの見方や考え方そのものがリセットされていくような感覚を覚えました。それと同時に、この著書で描かれている本来的な進化の捉え方は弊社が重視してきた“コモンズ”という考え方とも根底では非常にリンクすることが多いような印象を勝手ながら受けています。
福岡先生は、自然(ピュシス)をありのままに記述する言葉(ロゴス)であり、より解像度の高い表現こそが重要であると著書の中で説かれていますが、改めて、なぜ自然(ピュシス)の豊かさを回復することが重要だと思われるのか、その背景のお考えについて、ぜひお聞かせください。
“自然(ピュシス)の豊かさを回復する” 新たな思考を体験する万博パビリオン
福岡伸一(以下、福岡):ありがとうございます。
まず、具体的な話からする方がわかりやすいかなと思うのですが、今、私は2025年日本国際博覧会(略称「大阪・関西万博」)というイベントのテーマ事業と呼ばれる企画のプロデューサーの一人を拝命しております。この万博のテーマが「いのち輝く未来社会のデザイン」とされています。ここで、改めていのちを考えるというのが、この万博のテーマなんですね。テーマ事業のプロデューサーというのは、自分の考えに基づいてパビリオンをつくり、その中で何らかの展示をやる。建築やデザイン、あるいはビジョン、哲学を示すことが課せられた役割です。私は「いのち動的平衡館」というパビリオンをつくっています。建物は全体として、ふわりと細胞膜が地上に降り立ったような、ドーム状の形状をしております。
1970年に大阪万博があって、その時のテーマ館には岡本太郎が作った太陽の塔というものがあり、今も残っているわけです。あの時は「人類の進歩と調和」がテーマだったんですけれど、岡本太郎は人類は調和もしていないし進歩もしていないじゃないかということで、アンチテーゼとして縄文的な太陽の塔を建てたんですね。その岡本太郎の叫びと言いますか、意思を受け継いで、我々は新しくもう一度、いのちについて考えてみようと。
館の外観は、一枚の薄い膜が降り立ったような構造で、一柱が一本もなく、自分の力で立ち上がっている非常に自律的な建物です。我々がどこから来てどこへ行くのか? 生命とは何か? 生きているとはどういうことか? 生命の進化とはどういうことなのか? といったことを捉えようとしているわけですね。ここに私の生命哲学や坂本さんと語り合ったピュシスとロゴスの問題について議論したことをすべて投入しています。
しかし、限られた時間や展示スペースであまり難しい説明をしても万博のパビリオンとして楽しくないので、大人にも子どもにも分かりやすい展示方法を考えています。建物の内部には、「クラスラ」と名付けられた50万個もの立体LEDによって光の粒を描き出すシアターを作りました。それを使って、ここに「生命の物語」を再現しようとしています。
まず、はじめに、私たちはどこからきたのか?について、考えていきましょう。
自分の身体は自分のものであると通常は捉えていると思いますが、私たちの生命というのは38億年の生命の流れの中からやってきているわけです。いのち動的平衡館では、自分の身体の粒子が溶け出して大きな流れの中に合流し、生命のはじまりである一番最初に地球上に現れた初源的な細胞に戻ります。そこから進化のドラマが再現されて、現在の私たちに至るまでの38億年分のドラマを15分ぐらいで観せていきます。 “動的平衡”という生命哲学を、言葉ではなく体験として直感的に伝える展示を目指しました。

© DYNAMIC EQUILIBRIUM OF LIFE / EXPO2025
生命は“利他的な”革命によって、進化を遂げてきた
20世紀型のパラダイムですと、リチャード・ドーキンスが唱えた「利己的遺伝子論」というものがあります。我々生命体は遺伝子の乗り物であって、遺伝子とは単一の目的のためだけに生きているわけですね。単一の目的というのは自己増殖をするということです。遺伝子は自己増殖をするために非常に利己的に振舞ってきた、それが進化の大きな流れであると唱えているのが利己的遺伝子論なんです。確かに、適者生存のような進化の物語をそういう見方で見ると、より環境に適応して、より自分の子孫を残せる生物が生き残っている。遺伝子の視点から見ると非常に利己的に振る舞ってきたことによって現代の人間まで進化してきているように見えるというわけですね。
しかし、この20世紀型のパラダイムというのは少し古びてきているし、一元的すぎる見方なわけですね。生命の歴史を眺め渡してみると、ダイナミックな進化のジャンプが何回か起きています。一見すると、突然変異が起きて、その中で環境に適合するものが選び抜かれて生き残ったように見える側面ももちろんあるんですけれども、それだけではない。利己的ではなく、生命が「利他的に」振舞ったときこそ、生命は大きく進化しているんです。
この「利他」という言葉がキーワードなんです。生命38億年の歴史の中では、3回程度、利他的な革命があります。
第一は、単純な細胞が複雑な細胞になったこと。難しい言葉で言うと、原核細胞が真核細胞に進化したというイベントがあったんですね。単純な一枚の袋でとり囲まれている細胞の中に、ミトコンドリアとか、葉緑体とか、細胞角とか、細胞内小機関と呼ばれる複雑な仕組みができたのです。この進化によって生命は大きく前進しました。しかし、これは遺伝子が利己的に振舞ったからではないし、突然変異で急にこのような複雑なことが起こったわけでもないのです。大きい細胞と小さい細胞が出会って、普通だったら大きい細胞が小さい細胞を食べて栄養にしてしまっていたのを、そういう一方的な食う・食われるという関係性を、共生的な関係・利他的な関係に組み変えたんですね。大きい細胞は小さい細胞を取り込むけれども、それを細胞の中で破壊するのではなく、小さい細胞が大きい細胞の中の環境で守られながら、大きい細胞の中で増殖できるようにして、小さい細胞は得意なこと、エネルギー生産だったらエネルギー生産、太陽光線の補填であれば光合成という役割を担う。細胞の中にもう一つ小宇宙を作って、大きい細胞と小さい細胞が共存、共生するようなことが起こったので細胞が複雑化できた。これが第一の利他的な革命です。
第二の利他的な革命は、バラバラに存在していた単細胞生物が集合して、役割分担をして、より大きな多細胞生物を作ろうとしたときです。単に競争していたのではなく、得意なことを持ち寄るという利他的な共生によって、単細胞が多細胞化して、多細胞化することによってより大きな生命をつくることができる。この進化によって、今日の生命の多様性、ひいては人間のような多細胞生物を創り出すことができるようになったわけですね。
さらに、第三の利他的なジャンプ、革命が起こります。単純に細胞分裂で自分のコピーを再生産するクローン生殖(無性生殖)が主流だったところにオスとメスという性をつくって、その二つが協力しないと新しい生命が作れないという面倒くさい仕組みをつくったのです。しかし、そのことによって遺伝子をより積極的に交換・混合することができ、より新しい変化、生命の多様性を生み出したということなんですね。ここでも、オスとメスという不完全な存在が互いに他を必要として支える利他の関係があります。
このように考えていくと、利己的遺伝子論は利他的な共生論として書き直されるべきだと感じます。生態系全体の見方、地球環境全体を弱肉強食や優勝劣敗のような競争・闘争の歴史として見るのではなく、共生、利他性の歴史で見ていく。このような共生、利他性の生命観が「動的平衡の生命観」であり、「いのち動的平衡館」ではこれを来場者の皆さんと一緒に考えようとしていています。
また、生命は時間というものを持っていて、それは有限です。我々はどこからきているのか? というと、今お話ししたような38億年の生命の利他生の流れからきているわけですが、私たちはどこへいくのか? ということについて考えると、「死」という問題を避けて通れないわけです。死というのは一般的には遠ざけたいもの。なるべくなら考えたくないもの、あるいは恐ろしいもの、悲しいものとして捉えられていますけれども、これまた生命全体の流れを見るとですね、死ぬことというのは新しい生命に時間、場所、資源を手渡すということなのです。つまり、死は最大の利他的な行為とも言えるわけです。
いのち動的平衡館では、こういった生命の利他性を中心に、動的平衡の生命観をもう一度みんなで考えようというフィロソフィーを提案しようとしているわけなんです。はじめのご質問に戻りますが、ピュシスの豊かさというのは、つまり、生命の持っている利他性に気がつくということだ、と言い換えることができるのではないでしょうか。
小川:生命の壮大な流れの中に、利他性というものが在る、私たち自身の生命が一連の流れとして感じることができるというのは、非常に心が豊かになりますね。パビリオンを訪れるのが非常に楽しみです。ところで、このAru Societyプロジェクトのアドバイザーにも入っていただいている住田孝之さんという方が経産省時代に、万博の「いのち輝く未来社会のデザイン」というタイトルを名付けたと伺っています。当時、本当は “生命” という言葉をタイトルの頭に付けたかったこと、人間中心の目線ではなく、自然、つまり生命全体の総体的な考えから、このタイトルを考えたと仰っていました。
福岡:万博とは、歴史的には技術や新しい考え方によって新たな価値を生み出す産業振興も含めたイノベーション・テクノロジーのお祭りなので、70年万博の時も動く歩道や携帯電話の原型が展示されて、みんなが驚きました。今回も、新しいテクノロジーを見せるという側面、それが万博の主流の意義でもあります。
ただし、現代は新しいテクノロジーはこういうお祭りや催事で初めて見せなくても、ネット上にどんどん展開されているわけなので、もう少し新しい万博の意義が必要なんじゃないかということで、2025年の万博では、生命哲学や社会の新しいビジョンを考える場にしたいというのが、一つのコンセプトです。私は、その辺りを担当すべく頑張ってきました。
小川:素晴らしいですね。「生命とは何か?」という本質的な観点が盛り込まれた、普遍的な新たな社会ビジョンが生まれてくるであろうことを願っております。
では、次に先生にお伺いさせていただきたいテーマは「創造的進化」についてです。人間はどのような時代においても、挑戦すること、変化することを恐れずに何とか生き残り続けていく生き物でもあると思います。一方で、そのような進化が、気候変動、パンデミック、戦争など、あらゆる事象を起こし、ロゴス的なものの見方、人間中心のものの見方、考え方がさらなる変化を起こそうとしているのも、また事実ではあると思います。ご著書の中では、フランスの哲学者アンリ・ベルクソンの「創造的進化」の解釈をベースとしながら、動的平衡による先生独自の生命観について説かれていますが、より良い未来を創造するためにも、アンリ・ベルクソンが提唱する考え方を私たちはどのように捉えると良いのか、ご教示いただけますでしょうか。おそらく、創造的進化の真意を捉え直すことはイノベーションという変革の真意を問い直すことでもあると考えております。先生のお考えを是非お聞かせください。
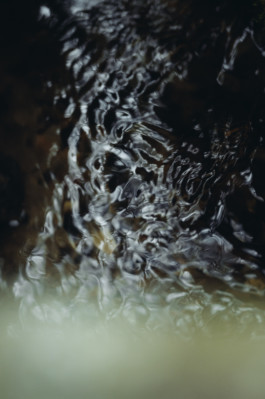
自然(ピュシス)の利他的な在り方、振る舞いを
人間はロゴス(言葉)の力によって取り戻すべき時にある
福岡:自然は、そもそもが競争や闘争をしているのではなく協力している、つまり、利他性によって支えられている状態です。これが、本来のピュシスの在り方なんですね。今お話したような進化のプロセスにおいても利他性が中心原理になっていますし、現在の地球環境でも、利他性はたくさんのところに見えてきます。
一番利他的に振舞ってくれているのが植物で、植物は太陽光線のエネルギーを光合成という作用によって有機物に変えてくれているわけですね。しかも植物は必要以上の量を作り、その余剰分をため込まずに他の生命に手渡してきました。もし植物が自分たちの生存に必要な分だけしか有機物を作っていなければ、つまり利己的に振る舞っていたら、他の生物が進化する余地はゼロでした。
植物が利他的に振る舞って、過剰に光合成をして、葉っぱを茂らせて、それを虫や鳥に食べさせ、葉が落ちて土壌を豊かにしてくれているわけですし、木の実や果物、穀物、お芋などは基本的に自分のためにエネルギーを作っているんですが、それをある意味惜しげもなく他の生物に与えてくれているわけですよね。それが草食動物を支え、あるいは昆虫を支え、また昆虫は花粉を媒介するような遠方的な働きを果たし、草食動物は動物性、肉食動物の餌になり、あらゆる動物はまた分解されて植物の栄養になったり、二酸化炭素になったりして地球環境が回っているという、自然本来のあり方、ピュシスの在り方とは利他性なわけです。
その中で人間だけが利己的に振舞っているのです。人間は自分が地球上で一番偉いと思っているし、自分が地球の支配者で、他の資源はみんな人間のためにあるというふうに思っている。地下に眠っていた自然資源の石油や石炭、天然ガスを掘り出してどんどん燃やして、二酸化炭素を空気中に増やしてきました。それを戻すのは本来植物の作用だったのですが、熱帯雨林を開発し、都市をつくり、植物をどんどん減らしているので、二酸化炭素の量が地球上に増えてしまっているというのが環境問題です。二酸化炭素そのものは悪者でもないし毒でもない。循環の一形態として、二酸化炭素が滞留していることが問題なのです。
人間だけが自然本来の在り方、利他的に振る舞うべき生命の在り方を忘れて、利己的に振舞ってしまっているのが現代社会です。そして、それを推進しているのが資本主義というものだとすると、そこを見直さないとならない。では、どうして人間だけが利己的に振る舞うようになったのでしょうか? 人間だけが、他の生物と違う文明を創り、テクノロジーを駆使し、あるいは、社会制度を創ったり経済を創ったり、貨幣を創ったりしています。
他の生物は基本的に富を蓄積していないわけです。もし過剰にあれば、それを必ず誰かに手渡している。なぜかというと、取っておいても仕方がないからです。何か資源を貯蓄しても、それは腐るかダメになるかなので、あらゆる生物は何かを過剰に生み出したり、得たときには、必ずそれを他者に手渡している。それが利他性です。植物ほどではなくとも、他の生物も多かれ少なかれ利他的に振る舞っているのに、人間だけが利己的に振る舞って、富を貯蓄し、私有財産を増やしてきました。
では、なぜ人間だけがピュシスの原則から外れて利己的に振舞っているのかというと、それは端的にいうと、ロゴスのせいなんですね。つまり、人間だけが言語を創り出し、言語の作用によって世界を構造化して、さまざまな社会システムを創り出しました。文明や、経済や、法律や、貨幣や、それらはすべてロゴスの産物なんです。言語には、コミュニケーションの道具としての側面があり、それは他の生物にも同様に存在します。鳥が鳴いたり、昆虫が羽を擦り合わせて歌を歌ったりというように、多くは求愛行動としてのコミュニケーションのツールとしての言語があるんです。
しかし人間は、コミュニケーションツールだけではなく、世界を構造化する、フィクションを創造するための道具として言語を用いたわけですね。このことによって文明ができ、経済ができ、社会制度や基本的人権を創り出せた。一人ひとりが生きている意味があり価値があるというのが基本的人権ですよね。それを保証しているのは、全てロゴス、言葉なんですね。男だろうが女だろうが、大人だろうが子供だろうが、障害を持った人や病気の人にも、それぞれ基本的人権があって生きる意味があり価値があるということを互いに約束できたのはロゴスの作用なので、人間が生み出したロゴスというのは素晴らしいものであるのは間違いがないわけです。
他の生物はロゴスを持っていないので、個々のいのちというのは自分で生きることができなくなればそれで終わりだし、何万個の卵を産んでもその卵一つ一つのいのちはそれほど重みを持たずに、他の生物に食べられたり流されたりしてしまうという、ピュシスの持っている残酷な側面というものがあるわけです。
人間だけが、ロゴスを作ったおかげで、個々のいのちに等しく価値があるという基本的人権の概念を生み出しました。本来のピュシスは素晴らしいんですけれど、残酷な側面を持っています。人間はロゴス的な言葉の作用によってピュシスの本来の残酷さから逃れて、個々の生命の価値を作り出したのです。
ただ、ロゴスには非常に負の側面というか、行き過ぎるとよくない側面があって、ピュシスを分節する力、切り分ける力があるのです。本来の自然は動的平衡の流れの中に、利他性の中にあって、それはあらゆるものが相互に繋がっているというのが本来のピュシスの在り方ですよね。
でもロゴスというのは、そういったある種の混沌とした自然を言葉の作用によって切り分けて、概念化して、整理して、その上に文化や文明を作っているわけです。それが非常に人間を人間たらしめていることではあるのですが……。例えば、ロゴスの作用で海とか川とか湖とか雨とか雪とか、水の流れを分節していますよね。河川だったら、国交相管轄で、海だったら水産庁管轄というふうに、管轄まで分節化されている。でも本当は、水の流れは一体的なものだし、海も川も雨も雪も、あるいは我々の身体の中を通り抜けていく水も本来は一連の流れなんですが、ロゴスの作用によって切り分けられて個別なものとして概念化されると、本来の有機的なつながり、動的平衡としてのつながりが見えなくなってしまう。ピュシスの動的な作用がロゴスによって分断されてしまう。
だからこそ、人間はロゴスを捨てることはできないけれど、ロゴスによって切り分けられすぎた、機械論的に見做されすぎたピュシスの在り方を回復することが大事なのです。そして、それもまた、ロゴスの、言葉の力によってしか回復できないのです。ピュシスをありのまま、ピュシスとして受け入れるのが良いとすると、人間はロゴスを手放して昔の動物世界に戻らざるを得ないですが、そんなことはできないですよね。人間がロゴスを持った特別な生物としてやらなければならないのは、切り分けられすぎたロゴスの作用というものに気がついて、その上で利己的になりすぎた人間の在り方を反省して、本来のピュシスの在り方を、新しい解像度の高いロゴス、言葉によって説明し直す。概念として取り戻すのが、今、我々が行わなければいけないことなんじゃないかなというのが、私の生命哲学なんです。
小川:ありがとうございます。生命の利他的な振る舞いの在り方へと立ち返ること、そこがまずは出発点となりそうですね。さらに、それを言葉によって表現し、人間の振る舞いという所作という新たな共通の認識を持つことが大切になってきますね。

常に自己破壊を繰り返しながら、つくり直すという生命の在り方
創造的進化の意義は、落ちていく坂を登り返す “努力” という営みにこそある
福岡:では、ここから、ご質問をいただいたベルクソンの創造的進化についてお話をしていきたいと思います。
動的平衡とは、あらゆるものが相互に繋がっているということを意味します。そして、絶えず物質もエネルギーも環境からやってきて、一瞬、我々の生命を形作るんですけれども、それはまた環境に放出されていって、大きな循環の中で覚醒酩酊があり、このように常に動的なものです。その動的な循環を回すために我々は何をしているのかというと、常に自己破壊をしていて、そしてまたつくり直すということをしているわけですね。だから、常に壊しながらつくり直すということを生命はしている。これもまた動的平衡のコンセプトの大事な部分です。
生命とAIというテーマで言いますと、AIがそのうち人間を凌駕してシンギュラリティを越えると、生命的なものになって人間を支配するんじゃないかと恐れられていますけれども、AIにできないことが一つあって、それは、自己を破壊しながら新しくつくり直すことですよね。AIは常にデータを溜めていく。履歴を増やしていって、その履歴の中から最適な解を選び出すということしかできない。でも、人間を含めた生命は常に自分を壊してつくり直すことができます。
百年前のフランスの哲学者アンリ・ベルクソンは、この生命の特性を「生命というのは物質が下る坂を上り返すような努力をしている」というふうに、自身の著書『創造的進化』の中で言いました。生命の持っている壊す作用というのは、まるで落ちていく坂を上り返すような努力だと、彼は見たわけです。これは非常に慧眼だったのですが、生命の原理について充分な知見が科学界からはまだなかった時期の言葉なので、哲学者の言葉として止まってます。もう少しこれを科学的な言葉で言い直すと、物質が下る坂というのは何かというと、「エントロピー増大の法則」によって説明ができます。エントロピー増大の法則は宇宙の大原則で、秩序のあるものは秩序のない方向にしか動かない。形あるものは形が崩れていく方向にしか動かない。時間の経過とはそういうもので、どんな壮麗なピラミッドのような立派な建造物でも、出来立てはピカピカですけれども、長い年月のあかにだんだん劣化して風化して砂粒に戻っていく。これがエントロピー増大の法則です。
整理整頓していた机や部屋も、ちょっと油断するとすぐに散らかったりゴミが溜まってしまったりする。これもエントロピー増大の法則です。あるいは淹れたてのコーヒーは熱いけれど、すぐにぬるくなってしまうのも、熱が拡散するということでエントロピー増大の法則ですよね。これが物質が下る坂で、放っておくと物質はエントロピー増大の法則に翻弄されながら、だんだん秩序をなくしていく。でも生命体だけはその坂をなんとか登ろうとする努力があるというふうに、ベルクソンは言っているわけです。確かに、細胞はすごく秩序が高いシステムですが、細胞膜は常に酸化されてしまう。活性酸素が降り注いできてどんどん錆びついてしまう。それから細胞の中には老廃物が溜まって、あるいはタンパク質の片生物が溜まっていったりします。放っておいたら生物もだんだんエントロピー増大の法則によって坂を転がり落ちてしまうんですけれども、生命体はそう簡単にエントロピー増大の坂を転がり落ちずに、その坂を必死に登り返そうとしているわけですね。
ベルクソンは、どうして上り返せるのかということを解き明かすことはできなかったのですが、私の提唱する動的平衡論では、それをこう解釈しています。
生命は自分自身を率先して破壊している。エントロピー増大の法則よりも速い速度で自らを壊している。壊すことによってエントロピーをどんどん捨てながら、新しくつくり直すことで、エントロピー増大の坂を登り返す営みをしているのです。それを“努力”とベルクソンは呼んだわけですが、まさに生命が持っているある種の健気さ、一生懸命さをいのちの輝きだとすれば、“いのち輝く” ということは、この坂を一生懸命登り返そうとしている、その営みにこそあると言えるわけですね。
しかし、生命はエントロピー増大の法則に一時的に抗うことはできても、ずっと勝ち続けることはできず、やがては、ずるずるとその坂を落ちていかざるを得ません。登り返そうとしているが、少しずつ後退していく。これが老化ということであり、最終的にはエントロピー増大の法則に打ち負かされるということは、つまり “死” を意味します。先ほども申し上げたように、死は個体としての生命の終わりですけれども、動的平衡の大きな流れの中では次の生命に引き継がれるので、死もまたバトンタッチであり利他的行為であると言えます。なので、創造的進化というベルクソンの言ったことのなかで一番大事なのは、壊しながら進んでいるということ。それは、動的平衡論のキーコンセプトでもあるわけです。
小川:先生の説明はとてもわかりやすいですね。何度もベルクソンの創造的進化の理論的な理解に努めようとしても、1日2ページぐらいしか読み進めることが出来ないほどに難解でしたが、先生の説明でよく理解できました。このような創造的進化のお話と利他性という本来の生命、生態系の在り方のお話は、非常に密接に絡んでいるのですね。
福岡:壊しながら、つくり直しているというのが地球環境本来の生態系であり、本来の生態系とは利他性というものを大切にしているので、人間が利己的に振る舞いすぎていることを反省するべきですね。威張るな人間!ということです。人間もエコシステムの一員であるならば、生命本来の動的平衡、そして利他的に振る舞うということをもう少し考え直さなければならない。利己的に振舞っていると、地球環境全体を損ねてしまって、それは結局人間にリベンジすることになるわけです。人間にとっては地球環境はなくてはならないことですけれども、地球環境にとっては人間はなくていいわけですから。そこを人間という生物は見誤ってはいけないということですね。
小川:本当にそう思います。謙虚さというものについて、自然、生命の在り方から私たちは学び直すべきときにありますね。
最後の質問になります。“シグナルとして取り出されたものではない、本来のノイズとしてのピュシスの場所に下りていくためには、客観的な観察者であることをいったんやめて、ピュシスのノイズの中に内部観察者として入っていかないといけいない。それはある意味で、非常にパーソナルな体験である。”(著書:音楽と生命(坂本龍一、福岡伸一共著、(株)集英社2023年発行))というご発言の記載がありました。これは、まさに、日本が培ってきた精神性や文化、芸術とも、深く繋がるものがあるのではないかと感じていますし、この感性を取り戻していくことは、関係を細分化し断ち切っていく、いわば、ロゴス的な考えのもと構築された、今の社会のありようへの違和感と変容をもたらすことができるかもしれないと考えます。また、このような考え方をロゴス、つまり、「共通言語 common language」として意味づけをし、日本、世界へと伝えていくことも、とても大事なことであると思います。改めて、自然(ピュシス)という豊かさを回復することをどのように表現することが望ましいとお考えでしょうか。
破壊的創造。イノベーションの本質は
ロゴスから、ピュシスへと立ち返るプロセスにこそ見出すことができる
福岡:地球環境にピュシスという言葉を当てはめると、利他性、動的平衡の関係性が成り立ち、あらゆるものが相互に繋がっている動的なものとして捉えることができます。それを人間のロゴスが分節化しすぎている。このロゴス的な捉え方を見直していかないといけない、というお話をしてきました。これは、坂本さんとの対談の中でも繰り返し語っていることです。坂本さんご自身も、最初はYMOの電子音楽のように、音楽というものをデジタル化して音符を分節化し、非常に再現性よく織り出すというところに面白さを感じて、一世を風靡しましたが、その後、やっぱりロゴス的に行き過ぎるというのは本来の音楽を追求する行為ではないと、だんだん自然音とかノイズとか、不協和音とか、デジタル音楽はシンクロナイズドミュージックですけれど、そうではない “アシンク” というところに回帰していきましたよね。
私もまた生物学者として、最初は遺伝子を一生懸命研究していたわけです。遺伝子というのは、ある意味生命のデジタル情報なので、遺伝子を解析するとデジタル暗号が読み解けて、生命のミクロなメカニズムがわかってくるわけですけれど、生命を情報化しすぎると、あるいはメカニズムとして捉えすぎると、生命の持っている本来の動的なもの、つながり、利他性、ピュシスというものを見失ってしまいます。私自身も、坂本さんがデジタルから自然音に戻ったように、分子生物学のデジタル的な遺伝子万能論というところから、もう少し統合的な生命論を打ち立てるべきだというふうに、自分の中でのパラダイムシフトとして、動的平衡論というものにシフトしていったわけです。
だから、坂本さんと私は音楽家と生物学者という全然違うフィールドで活動していて、本来はご縁がなかったはずなんですけれども、お話をする機会があり、だんだん意気投合していく中で同じことを考えているのだな、ということを相互に分かってきました。人生のプロセスは、少年時代はピュシスとして生きていても、勉強していくというのはロゴス化されていくということです。その中で、彼は音を切り分けていくという音楽理論にデジタル音楽の方向に、私は生命を切り分けてミクロな解析をする、遺伝子を解析するという方法のデジタル的なものに最初は行きました。それは、人間が何かを学ぶ、勉強するということは基本的にはロゴス的に物事を究明するということなので仕方がないプロセスなんですが、ロゴス的なところに行き過ぎると、本来的なピュシスを見失ってしまうということで、ある時点でピュシスに回帰して行っているというのが、二人の同じような人生の航路なわけですよね。同じだったから、馬が合うというふうにも考えられるんではないかなと。
「ロゴスから、ピュシスへ」という旅路は誰もがありうることです。それぞれ一人ひとり、このモデルを考え直されてみてもいいんじゃないかなと思うわけです。一人ひとりが立ち返っていくことの重要性はそういうところにあるんじゃないかと思います。
小川:ロゴスから、ピュシスへとそれぞれが自ら壊しながら、またつくり直していくということ。その行為自体がピュシスの本質に返っていくということでもあるのでしょうか?
福岡:いきなりピュシスのところに行くとですね、宇宙は全部繋がっているみたいな、ちょっとスピリチュアルな感じになってしまうんです。私と坂本さんがそれなりに頑張ってきたと思うのは、一度はロゴス的な方法での究極を見極めた上で、それだけでは世界を十分説明しきれないから、ピュシスの本来の在り方はそうではないということに気がついて、その反省の上に、逆に戻ってきたことです。そういう過程が必要なんじゃないかなと思うわけですね。
小川:そうですね。一度は坂を登り切ってから立ち返るということのゆらぎこそが重要な観点だということですよね。今は社会も世界も、大きなパラダイムシフトを迎えている、いわば転換期にある。今、企業も本来は自然の摂理と同じように常につくり直しながら、落ちていく坂を登り返していく活動そのものがなければ、生き残っていくことが難しくなる時代に置かれていると感じています。企業の活動というところにもこのようなお話を置き換えて、お話をしていけるといいなと思いました。まさに利他性という共に在ることを考えていくことを、私たち自身の役割としてやらないといけないなと改めて感じています。
福岡:今日私がお話ししたことをうまくトランスレートしていただけたらいいなと思います。どんなお仕事をしている方も本来の自然とそれを切り分けていくロゴスのジレンマみたいなものがあるはずです。地球環境に本当に適ったものがピュシスですが、そうすると企業活動というのは究極のロゴス活動ですから、そこに相反があるというのは確かなのですよね。いかにその二つを往復しながら新たな道を見つけていけるかというのが21世紀の課題だと思いますし、社会や環境のことを配慮しながら、経済活動をしましょうということです。ロゴス、つまり利潤追求ということだけ求めていると企業もロゴス化していくということですよね。地球本来の在り方とピュシスをどう回復していくのかということが課題となっているし、それが万博のテーマでもあります。御社が考えておられるようなAruSocietyの目標とも重なってくるんじゃないかと思います。
小川:私たちがやるべきなのは、利潤の最大化ではなく「価値の最大化」というところなのかなというのは考えています。価値の最大化について考えていくと、常につくっては壊しというのが繰り返されるうちに、どんどん価値がアップデートされていくということですものね。
福岡:動的平衡であり、ベルクソンがいう創造的進化の中の破壊という話は、壊れたから取り替えるとか、古くなったから交換するという意味の新陳代謝じゃないんですよね。出来立てほやほやでも、まだまだ使えるにも関わらず、どんどん壊していくというのが動的平衡の破壊だし、実際に細胞の中で起きている破壊も同じです。つまり、率先してどんどん破壊しているわけです。そうしないと、エントロピー増大の法則に打ち勝って、転がる坂を登り返すように生きていけない。単なる破壊じゃなくて、破壊的創造と言うか。
小川:先生のお話を根底に置いて、企業のイノベーションの本質を捉え直してみると、創造的進化の捉え方、利他性という自然の在り方、私たちは常に破壊しながら創造していくという動的な動きをあらゆる状況で回復させていくことの先に、次の時代の社会の在り方が見えてくるのではないかと改めて感じることができました。福岡先生、今日は本当にありがとうございました。
index











contents
© Loftwork Inc. All rights reserved
index











contents
© Loftwork Inc. All rights reserved